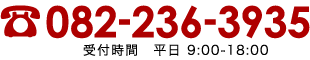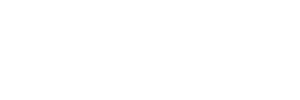ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
防御は最大の攻撃
2014/06/20 14:02:22 株式投資
コメント (0)
「攻撃は最大の防御」という言葉があります。スポーツや戦いにおいて、自ら攻撃に出ている間は相手は守りに入るわけだから、相手に攻め入る時を与えないことこそが、すなわち自らを守ることにもなる、ということです。
ところで、株式投資などの資産運用についてはどうでしょうか?私の経験からすれば、「防御こそが最大の攻撃」であると言えると思います。
なぜなら、資産運用はたとえ「100勝1敗」であったとしても、その1敗が致命的な失敗であれば全財産を失うこともあるからです。バブル期に株式投資で一大財産を築いた方、ITバブル期のカリスマトレーダーが、今はどうなっているのでしょうか・・・
資産運用は、正直、勝てるときは素人でも十分勝てます。でも、その時の成功体験がその人の思考回路を狂わせるのです。「この方法なら、未来永劫勝ち続けることができるかも・・」と。
しかし、残念ながら高度成長期、安定成長期は、もう日本には訪れないでしょう。発展途上の国においても成長期のスパンは、すぐに外資に蹂躙されるこのご時世では、かなり短くなっています。世界的に経済環境の変化は激しく、連鎖的になっています。
その中で、同じ「攻めの投資戦術」に固執してしまうと、間違いなく負けます。1~2年は勝つことができても、5年、10年のスパンでは必ず負けるでしょう。そのやり方が通用しなくなっても、「守り」に切り替えることができないからです。
大事な資産は「守って」ください。インフレや円安による「目減り」から守ってください。その資産は、あなたの老後資金であり、子どもや孫の教育資金であり、だれかの幸せのために使われるべき資産なのですから。
10年のうち、「攻め」で勝てるのはせいぜい2~3年くらいでしょう。残りの7~8年を守りぬくことができてこそ、攻めの2~3年を見極めることができ、そこで資産を増やすことができるのです。
とりあえず今すぐ止めるべきことは、「リスク資産を持ちっぱなしにすること」です。四六時中、下落リスクにさらされていては、守りきれません。リスク資産を持っていいのは、10年のうち攻めの2~3年だけです。守りの時は、預貯金か、インフレに強い低リスク資産に切り替えましょう。どうしても株式運用したいなら、短期投資に徹してください。
個人投資家のうち、市場で生き残れるのは1割と言われています。それなら、下手に手出しをするのをやめるか、1割に残れる本当の強さを身につけましょう。
ところで、株式投資などの資産運用についてはどうでしょうか?私の経験からすれば、「防御こそが最大の攻撃」であると言えると思います。
なぜなら、資産運用はたとえ「100勝1敗」であったとしても、その1敗が致命的な失敗であれば全財産を失うこともあるからです。バブル期に株式投資で一大財産を築いた方、ITバブル期のカリスマトレーダーが、今はどうなっているのでしょうか・・・
資産運用は、正直、勝てるときは素人でも十分勝てます。でも、その時の成功体験がその人の思考回路を狂わせるのです。「この方法なら、未来永劫勝ち続けることができるかも・・」と。
しかし、残念ながら高度成長期、安定成長期は、もう日本には訪れないでしょう。発展途上の国においても成長期のスパンは、すぐに外資に蹂躙されるこのご時世では、かなり短くなっています。世界的に経済環境の変化は激しく、連鎖的になっています。
その中で、同じ「攻めの投資戦術」に固執してしまうと、間違いなく負けます。1~2年は勝つことができても、5年、10年のスパンでは必ず負けるでしょう。そのやり方が通用しなくなっても、「守り」に切り替えることができないからです。
大事な資産は「守って」ください。インフレや円安による「目減り」から守ってください。その資産は、あなたの老後資金であり、子どもや孫の教育資金であり、だれかの幸せのために使われるべき資産なのですから。
10年のうち、「攻め」で勝てるのはせいぜい2~3年くらいでしょう。残りの7~8年を守りぬくことができてこそ、攻めの2~3年を見極めることができ、そこで資産を増やすことができるのです。
とりあえず今すぐ止めるべきことは、「リスク資産を持ちっぱなしにすること」です。四六時中、下落リスクにさらされていては、守りきれません。リスク資産を持っていいのは、10年のうち攻めの2~3年だけです。守りの時は、預貯金か、インフレに強い低リスク資産に切り替えましょう。どうしても株式運用したいなら、短期投資に徹してください。
個人投資家のうち、市場で生き残れるのは1割と言われています。それなら、下手に手出しをするのをやめるか、1割に残れる本当の強さを身につけましょう。
税務調査対策(3) 税理士を替えると、調査が来る?
2014/06/09 14:29:56 税務調査
コメント (0)
「税理士を替えると、税務調査が来ませんか?」
よく聞かれます。聞かれる度に、いつも不思議に思っています。なぜなら、毎年50件超の税務調査について立ち会ったり、情報交換したりしていますが、「税理士が替わったから、来た」と思われる調査を一度も見たことがないからです。
税務調査対策(1)でも書きましたが、平成24年事務年度の実地調査割合は、目標の8.5%に対して実績が3.1%です。税務当局は十分な実地調査に赴けていないのです。それでも、前回不正のあった納税者や、売り上げが大きく伸びたのに利益が全然出ていない法人に対しては、優先的に調査しないといけないでしょう。税務当局も手一杯なのです。そんな状況下で、あなたが調査官だったとしたら、「あの法人は税理士が替わりました。他に理由はないですが、なんとなく何か出るかもしれないので、調査に行きます」と上席に言えますか?言えないですよね・・
いわば都市伝説化しているわけですが、なぜこういった話が根強いのでしょうか。ここからは想像ですが、内部者からの告発など、いわゆるタレコミからの脱税情報により税務調査が行われることも少数ながらあると聞きます。税理士としても、「こんな申告内容では顧問はできない」として関与が切れることもあると思います。そんなタイミングが重なって行われた税務調査に対して、「税理士が替わったから・・」となっていったのではないでしょうか。
よく聞かれます。聞かれる度に、いつも不思議に思っています。なぜなら、毎年50件超の税務調査について立ち会ったり、情報交換したりしていますが、「税理士が替わったから、来た」と思われる調査を一度も見たことがないからです。
税務調査対策(1)でも書きましたが、平成24年事務年度の実地調査割合は、目標の8.5%に対して実績が3.1%です。税務当局は十分な実地調査に赴けていないのです。それでも、前回不正のあった納税者や、売り上げが大きく伸びたのに利益が全然出ていない法人に対しては、優先的に調査しないといけないでしょう。税務当局も手一杯なのです。そんな状況下で、あなたが調査官だったとしたら、「あの法人は税理士が替わりました。他に理由はないですが、なんとなく何か出るかもしれないので、調査に行きます」と上席に言えますか?言えないですよね・・
いわば都市伝説化しているわけですが、なぜこういった話が根強いのでしょうか。ここからは想像ですが、内部者からの告発など、いわゆるタレコミからの脱税情報により税務調査が行われることも少数ながらあると聞きます。税理士としても、「こんな申告内容では顧問はできない」として関与が切れることもあると思います。そんなタイミングが重なって行われた税務調査に対して、「税理士が替わったから・・」となっていったのではないでしょうか。
税務調査対策(2) これだけは覚えておいて下さい!調査中の注意点
2014/06/02 15:48:51 税務調査
コメント (0)
通常の税務調査では、直近の過去3年分を調べる、ということがほとんどです。ですので税務調査は最短だと3年おきにやってくることになります。ただ実際は、前回お話した通り、税務署側の人手不足もあるために5~10年くらいの間隔がほとんどです(前回、悪質な所得隠し等を指摘された場合は別です)。
そもそも、税務調査は必ず受けないといけないのでしょうか。通常の税務調査は「任意調査です」と聞くと、「任意?じゃあ、受けても受けなくてもいいの?」と思われる方も多いのではと思います。結論から言いますと、受けないことはできません。「任意」の一方で、税法では納税者に「受任義務」というものを課しています。「なあんだ」という感じですが、ただいわゆる「マルサ」などの強制調査ではありませんので、指定された日時に大事な商談が入っていたり、体調不良だったりするときに日程を変更してもらうことは可能です。何にせよ、調査日程に関しては顧問税理士にも連絡が行きますので、よく話し合ってから決めることが大切です。
そして、実際の調査が始まると、調査官から色々な質問をされます。どこまで答えないといけないのでしょうか?調査官は「質問検査権」というものを持っています。「税務調査に必要があるときは、質問し、帳簿書類等の提出を求めることができる」この権利はかなり強力で、これがある限り、質問に対して拒絶することはできません。
ただ、「税務調査に対して」ですので、たとえばプライベートの引き出しの中やパソコンのデータまで勝手に見ることはできません。調査官が勝手に触ることは違法調査です。開示を求められたら、まずその理由を確認し、必要なものだけをこちらから開示するようにしましょう。
特に覚えておいていただきたいのは、質問に対して「拒絶」や「ウソ」はいけませんが、かと言って即答する必要もありません。あいまいな回答は調査に不利な影響を及ぼすかもしれませんので、そういう時は「よく確認して回答します」と言ってその日は回答を保留し、調査官が帰ってから顧問税理士とよく相談してから後日回答するようにするか、税理士に回答してもらいましょう。
そもそも、税務調査は必ず受けないといけないのでしょうか。通常の税務調査は「任意調査です」と聞くと、「任意?じゃあ、受けても受けなくてもいいの?」と思われる方も多いのではと思います。結論から言いますと、受けないことはできません。「任意」の一方で、税法では納税者に「受任義務」というものを課しています。「なあんだ」という感じですが、ただいわゆる「マルサ」などの強制調査ではありませんので、指定された日時に大事な商談が入っていたり、体調不良だったりするときに日程を変更してもらうことは可能です。何にせよ、調査日程に関しては顧問税理士にも連絡が行きますので、よく話し合ってから決めることが大切です。
そして、実際の調査が始まると、調査官から色々な質問をされます。どこまで答えないといけないのでしょうか?調査官は「質問検査権」というものを持っています。「税務調査に必要があるときは、質問し、帳簿書類等の提出を求めることができる」この権利はかなり強力で、これがある限り、質問に対して拒絶することはできません。
ただ、「税務調査に対して」ですので、たとえばプライベートの引き出しの中やパソコンのデータまで勝手に見ることはできません。調査官が勝手に触ることは違法調査です。開示を求められたら、まずその理由を確認し、必要なものだけをこちらから開示するようにしましょう。
特に覚えておいていただきたいのは、質問に対して「拒絶」や「ウソ」はいけませんが、かと言って即答する必要もありません。あいまいな回答は調査に不利な影響を及ぼすかもしれませんので、そういう時は「よく確認して回答します」と言ってその日は回答を保留し、調査官が帰ってから顧問税理士とよく相談してから後日回答するようにするか、税理士に回答してもらいましょう。
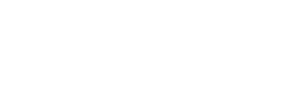

 RSS 2.0
RSS 2.0