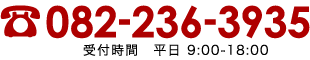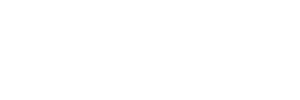ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
退職金を自分で準備する方法
2023/03/01 17:56:31 節税
コメント (0)
退職金は、数十年働いたことに対する自分自身への最後の対価です。リタイア後のことを考えるといくらあってもいい!と思いますが、経営者・事業者の方は、自分で準備しておかないと誰も準備してくれません。
もちろん給与・賞与の一部を貯蓄していく形でもいいのですが、退職金として準備するほうが税務的なメリットは大きくなります。①一定の方法で準備(積立)することで、その積立金が経費や所得控除になる、②退職金として受け取ったときの税金が優遇されている、③受け取った退職金は社会保険料等の対象にならない、などです。
とは言え、中退共や特退共といった毎月退職金を積み立てていく制度は、従業員さんには使えても経営者自身には使えませんので、下記の3つの商品を組み合わせて積み立てます。
(1)倒産防止共済を使う
意外に思われるかもしれませんが、倒産防止共済は退職金準備に使うほうがいいと思います。倒産防止共済は年額240万円、累計800万円をマックスに積み立てができ、積み立てなのに全額経費にできるので今や数少ない節税商品の一つですが、最大のデメリットは解約時に全額利益に上がることです。適当な時期に解約してしまうと、解約時に節税した税金を全部吐き出すことになるので、実は使い勝手が難しいのですが、これを退職金積立金と位置づけてしまいます。
800万円まで積み立ててずっと置いておき、退職金を支給する時にこれを解約して全額退職金に充てることで、解約益が全額退職金という経費で相殺され、解約にかかる税負担が発生しません(法人の場合)。また途中での一部解約はできませんが、積み立てておけば契約者貸付も受けられるので、一時的な運転資金借入の担保にもなります。
(2)生命保険を使う
800万円ではとても足りない!という場合には退職金の2階部分という意味合いで法人契約の生命保険を使います。なだらかに解約返戻率が上がっていき、リタイア予定時に返戻率がピークにくる長期平準定期保険などがいいと思います。退職金を3,000万円準備したいなら、生命保険で2,200万円を積み立てるイメージです。以前ほどではないにせよ一部節税効果もありますし、生命保険本来の目的である死亡保障等がつくので、経営リスクも減少できます。トータルメリットが大きいので、法人契約の生命保険は一本はほしいです。ただし損金性のないドル建て変額保険などを勧められた場合は、本当に今ベターな保険商品なのか検討する必要がありますので、契約前に一度ご相談いただければと思います。
(3)小規模共済共済を使う
うちは法人じゃない!という方は小規模共済で積み立てます。こちらも全額所得控除になる積立金です。不動産貸付業の個人や、法人の役員(医療法人、NPO法人等は不可)でも加入できます(契約自体は個人)。小規模共済は一括でも年金形式でも受け取ることができます。
もちろん給与・賞与の一部を貯蓄していく形でもいいのですが、退職金として準備するほうが税務的なメリットは大きくなります。①一定の方法で準備(積立)することで、その積立金が経費や所得控除になる、②退職金として受け取ったときの税金が優遇されている、③受け取った退職金は社会保険料等の対象にならない、などです。
とは言え、中退共や特退共といった毎月退職金を積み立てていく制度は、従業員さんには使えても経営者自身には使えませんので、下記の3つの商品を組み合わせて積み立てます。
(1)倒産防止共済を使う
意外に思われるかもしれませんが、倒産防止共済は退職金準備に使うほうがいいと思います。倒産防止共済は年額240万円、累計800万円をマックスに積み立てができ、積み立てなのに全額経費にできるので今や数少ない節税商品の一つですが、最大のデメリットは解約時に全額利益に上がることです。適当な時期に解約してしまうと、解約時に節税した税金を全部吐き出すことになるので、実は使い勝手が難しいのですが、これを退職金積立金と位置づけてしまいます。
800万円まで積み立ててずっと置いておき、退職金を支給する時にこれを解約して全額退職金に充てることで、解約益が全額退職金という経費で相殺され、解約にかかる税負担が発生しません(法人の場合)。また途中での一部解約はできませんが、積み立てておけば契約者貸付も受けられるので、一時的な運転資金借入の担保にもなります。
(2)生命保険を使う
800万円ではとても足りない!という場合には退職金の2階部分という意味合いで法人契約の生命保険を使います。なだらかに解約返戻率が上がっていき、リタイア予定時に返戻率がピークにくる長期平準定期保険などがいいと思います。退職金を3,000万円準備したいなら、生命保険で2,200万円を積み立てるイメージです。以前ほどではないにせよ一部節税効果もありますし、生命保険本来の目的である死亡保障等がつくので、経営リスクも減少できます。トータルメリットが大きいので、法人契約の生命保険は一本はほしいです。ただし損金性のないドル建て変額保険などを勧められた場合は、本当に今ベターな保険商品なのか検討する必要がありますので、契約前に一度ご相談いただければと思います。
(3)小規模共済共済を使う
うちは法人じゃない!という方は小規模共済で積み立てます。こちらも全額所得控除になる積立金です。不動産貸付業の個人や、法人の役員(医療法人、NPO法人等は不可)でも加入できます(契約自体は個人)。小規模共済は一括でも年金形式でも受け取ることができます。
「収入300万円以下は雑所得」の意味するところ
2022/09/01 15:39:56 節税
コメント (0)
国税庁が8/1に出した所得税の通達(法令解釈)の改正案が話題になっています。通達は税法そのものではないですが、「国税当局としてはこう解釈して税法を運用しますよ」という指針になります。そして話題になっている内容は、「収入金額(=年売上高)が300万円以下のものは、原則雑所得」という一文です。
今まで個人で事業・副業をしていて確定申告をする場合、それが「対価を得て継続的に行う事業」の場合は「事業所得」、そこまでではないものは「雑所得」と区分されていました。じゃあ具体的に事業所得と雑所得の境目ってどこよ?と聞かれると、はっきり決められていなかったので、実際のところ本人が「これは事業よ」と言えば事業所得、みたいなわりとアバウトな感じもありました。今回、今さらながらその境目が示された形です。(なお所得税の取り扱いなので、法人には関係ありません。)
では事業所得と雑所得で何が変わるのかという点ですが、両者とも売上から経費を引いた残りが利益で、それに対して累進課税で所得税が課される、という部分は同じです。異なるのは、雑所得の場合①青色申告特別控除(10~65万円)が受けられない、②青色事業専従者給与が支給できない(白色申告の事業専従者控除も取れない)、③損失が出た場合他の所得と損益通算(=相殺)ができない、という点になります。他にも純損失の繰越控除ができない、30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えない、などもあります。
①②の意味するところは、事業を行って利益が出た場合、「がっつりやらないと税金計算の時の優遇を受けさせないよ」ということになります。日本政府は副業を推進してるのだからがっつりやりなよ、と言いたいのかもしれませんが、努めている会社が副業禁止でこっそりやっている程度では税金は優遇されない、という不公平感が出る気がしますね。
また③は流行りの「サラリーマン節税」を封じる意味があります。書店でこれ関連の書籍がたくさん並んでいますが、例えば売上を10万円、経費を(入れれるだけ入れ込んで)200万円計上し、赤字の△190万円を給与所得と相殺する申告をして、給与から天引されていた所得税を還付してもらう、みたいなスキームです。ほぼ税金還付を目的にしている事業なんか、事業じゃないだろう!という税務当局の言いたいことはわかりますが、事業の黎明期で本当に赤字がかさんでいる場合も杓子定規に相殺を認めないのか、という問題も出てきます。
なおこの内容は8/31までパブリックコメントを募集しており、その内容によっては原案が修正される可能性があります。また改正が施行された場合、令和4年分以後の所得税について適用されます。つまり令和4年1月以降の事業までさかのぼって影響を受けますので、ご注意ください。
今まで個人で事業・副業をしていて確定申告をする場合、それが「対価を得て継続的に行う事業」の場合は「事業所得」、そこまでではないものは「雑所得」と区分されていました。じゃあ具体的に事業所得と雑所得の境目ってどこよ?と聞かれると、はっきり決められていなかったので、実際のところ本人が「これは事業よ」と言えば事業所得、みたいなわりとアバウトな感じもありました。今回、今さらながらその境目が示された形です。(なお所得税の取り扱いなので、法人には関係ありません。)
では事業所得と雑所得で何が変わるのかという点ですが、両者とも売上から経費を引いた残りが利益で、それに対して累進課税で所得税が課される、という部分は同じです。異なるのは、雑所得の場合①青色申告特別控除(10~65万円)が受けられない、②青色事業専従者給与が支給できない(白色申告の事業専従者控除も取れない)、③損失が出た場合他の所得と損益通算(=相殺)ができない、という点になります。他にも純損失の繰越控除ができない、30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えない、などもあります。
①②の意味するところは、事業を行って利益が出た場合、「がっつりやらないと税金計算の時の優遇を受けさせないよ」ということになります。日本政府は副業を推進してるのだからがっつりやりなよ、と言いたいのかもしれませんが、努めている会社が副業禁止でこっそりやっている程度では税金は優遇されない、という不公平感が出る気がしますね。
また③は流行りの「サラリーマン節税」を封じる意味があります。書店でこれ関連の書籍がたくさん並んでいますが、例えば売上を10万円、経費を(入れれるだけ入れ込んで)200万円計上し、赤字の△190万円を給与所得と相殺する申告をして、給与から天引されていた所得税を還付してもらう、みたいなスキームです。ほぼ税金還付を目的にしている事業なんか、事業じゃないだろう!という税務当局の言いたいことはわかりますが、事業の黎明期で本当に赤字がかさんでいる場合も杓子定規に相殺を認めないのか、という問題も出てきます。
なおこの内容は8/31までパブリックコメントを募集しており、その内容によっては原案が修正される可能性があります。また改正が施行された場合、令和4年分以後の所得税について適用されます。つまり令和4年1月以降の事業までさかのぼって影響を受けますので、ご注意ください。
確定申告しないほうがいい人、したほうがいい人
2020/02/03 18:02:54 節税
コメント (0)
今年も確定申告の時期が近づいて参りました。今回は、そもそも確定申告って何なの?誰がしないといけないの?というところからお話させていただきます。
法律的には「確定申告」という用語は法人の決算にもあてはまるのですが、一般的には確定申告といえば個人の申告です。毎年3月15日までに、個人の前年1年間に得た全ての所得を合算して、所得税額を税務署に自己申告して納めます。住民税や事業税、国民健康保険料などもその申告をもとに自治体が計算します。
ただし1か所からの給与収入しかない方は、会社が年末調整をしてくれます。これは確定申告を会社が代わりにやってくれるようなもので、この方は確定申告の義務はありません。
個人で商売をされている方や、賃貸不動産のオーナーなどは確定申告をしないといけない、というのはわかると思いますが、中には微妙なケースも出てきます。例えば、会社勤めで基本的には1か所からの給与収入なんだけど、他に少し副収入もある、という場合です。どのくらい副収入があれば確定申告しないといけないのかご存じですか?
所得税法の規定では、「メインの給与以外の給与収入」+「給与・退職金以外の所得」が20万円を超えると確定申告をしなければならないとされています。例えば副収入が18万円の給与収入のみなら確定申告をしなくていいし、給与収入が25万円ならしないといけません。また、個人年金収入が120万円あっても所得換算で18万円なら確定申告をしなくていいし、会社に内緒でこっそりやってるネット販売事業の売上が300万円あっても経費を差し引いたら利益(所得)が15万円だ、という方も確定申告不要です。下線部の「収入」と「所得」は、このような違いが出てくるので注意が必要です。ほんとは確定申告しなくていいのに、してしまった結果追加の所得税が出たら、それは納めないといけなくなりますので。
ところで、確定申告をしなくていいことが分かったから、はい確定申告さようなら、と言うのは少し早いです。確定申告の義務はないが、あえてすることで税金の還付や、住民税の軽減につながるケースが多々あるからです。
医療費控除など、年末調整ではできない控除があるから、というのが一番わかりやすいですが、それ以外でも例えば先ほどの、給与の副収入が18万円というケース。給与からは通常源泉所得税が天引きされていますので、合算して所得税を再計算した結果、副収入の所得税は引かれすぎだから還付される、というケースがあります。この場合は、まず計算してみて、税金が還ってきそうなら申告する、税金が追加になりそうなら申告をやめるのが正解です。
最後に、最近よくある注意点が、ふるさと納税のワンストップ特例です。これは5か所までのふるさと納税につき確定申告不要で住民税の控除をしてくれるのですが、医療費控除などのふるさと納税に関係ない確定申告をした場合でもワンストップ特例が無効になります。確定申告時にふるさと納税の寄付金控除も忘れず申告に加えてください。
法律的には「確定申告」という用語は法人の決算にもあてはまるのですが、一般的には確定申告といえば個人の申告です。毎年3月15日までに、個人の前年1年間に得た全ての所得を合算して、所得税額を税務署に自己申告して納めます。住民税や事業税、国民健康保険料などもその申告をもとに自治体が計算します。
ただし1か所からの給与収入しかない方は、会社が年末調整をしてくれます。これは確定申告を会社が代わりにやってくれるようなもので、この方は確定申告の義務はありません。
個人で商売をされている方や、賃貸不動産のオーナーなどは確定申告をしないといけない、というのはわかると思いますが、中には微妙なケースも出てきます。例えば、会社勤めで基本的には1か所からの給与収入なんだけど、他に少し副収入もある、という場合です。どのくらい副収入があれば確定申告しないといけないのかご存じですか?
所得税法の規定では、「メインの給与以外の給与収入」+「給与・退職金以外の所得」が20万円を超えると確定申告をしなければならないとされています。例えば副収入が18万円の給与収入のみなら確定申告をしなくていいし、給与収入が25万円ならしないといけません。また、個人年金収入が120万円あっても所得換算で18万円なら確定申告をしなくていいし、会社に内緒でこっそりやってるネット販売事業の売上が300万円あっても経費を差し引いたら利益(所得)が15万円だ、という方も確定申告不要です。下線部の「収入」と「所得」は、このような違いが出てくるので注意が必要です。ほんとは確定申告しなくていいのに、してしまった結果追加の所得税が出たら、それは納めないといけなくなりますので。
ところで、確定申告をしなくていいことが分かったから、はい確定申告さようなら、と言うのは少し早いです。確定申告の義務はないが、あえてすることで税金の還付や、住民税の軽減につながるケースが多々あるからです。
医療費控除など、年末調整ではできない控除があるから、というのが一番わかりやすいですが、それ以外でも例えば先ほどの、給与の副収入が18万円というケース。給与からは通常源泉所得税が天引きされていますので、合算して所得税を再計算した結果、副収入の所得税は引かれすぎだから還付される、というケースがあります。この場合は、まず計算してみて、税金が還ってきそうなら申告する、税金が追加になりそうなら申告をやめるのが正解です。
最後に、最近よくある注意点が、ふるさと納税のワンストップ特例です。これは5か所までのふるさと納税につき確定申告不要で住民税の控除をしてくれるのですが、医療費控除などのふるさと納税に関係ない確定申告をした場合でもワンストップ特例が無効になります。確定申告時にふるさと納税の寄付金控除も忘れず申告に加えてください。
増資って何?メリット・デメリットと税務上の注意点
2019/12/02 19:50:29 節税
コメント (0)
最初に会社を設立するときには、その会社の事業の元手として出したお金を資本金として会社に入れます。お金を出した人は株主となり、法律上その会社の所有者となります。増資とは、会社設立後に追加で資本金を増やすことを言います。
大きく見ると、会社の資金調達の種類は2種類しかなく、返さなくていいお金(資本金など=自己資本)と、返さないといけないお金(借入金など=他人資本)に分けられます。資本金が増えるということは、会社にとっては返さなくていいお金が増えることになり、それだけ財務基盤が強化されることになります。増資の方法には、追加で資金を入れる方法(有償増資)以外に、お金を入れないで会計処理上だけで資本金を増やす方法(無償増資)、また無償増資の方法の一つとして、借入金を資本金に組み入れる方法(DESという)などもあります。
増資の時に注意しないといけないのは、知らず知らずのうちに株主間で贈与関係が発生し、贈与税を払わないといけなくなることがあるということです。例えば100株=100万円を株主Aさんが出資して会社を新しく作って、その会社が儲かって1,000万円の利益を出したとします。その後Bさんが、俺にも出資させてくれと、Aさんと同条件で100株=100万円を追加出資したとします。
これでBさんには53万円の贈与税がかかってしまいます(AさんとBさんが親子でないと仮定)。なぜだか分かりますか・・?
Bさんが出資する直前、Aさんの所有する100株は、出資金100万円+利益1,000万円=1,100万円の価値(時価)があります。ここでBさんが出資すると、会社の価値総額は1,100万円+Bさん出資金100万円=1,200万円。この時点で株主はAさん100株、Bさん100株なので、合計200株。AさんとBさんの株式価値はそれぞれ1,200万円×100/200株=600万円になります。
Aさんの株式の価値は1,100万円から600万円に減ってしまいました。一方Bさんは100万円出資しただけなのに600万円の価値を手にしました。これは実質AさんからBさんに500万円の価値が移転したということになり、「実質的に贈与があった」とみなされるからです。そうならないためには、Bさんは100株を1,100万円で取得しなければいけません。
資本金が増えると、法人の納税額にも影響が出ます。ひとつは法人市民税の均等割です。資本金が1,000万円以下ですと年額5~12万円、それ以上1億円以下で13~15万円、1億円超10億円以下で16~40万円、といった具合です(広島市の場合。厳密には資本金「等」で判定)。
また資本金が1億円を超えると、法人税法上(中小企業ではなく)大法人とみなされます。こうなると、軽減税率の不適用、交際費の一部損金不算入、留保金課税、30万円未満の資産の全額損金算入特例の不適用、繰越欠損金の一部使用不可、法人事業税の外形標準課税適用(赤字でも事業税が発生する)など、さまざまな特例措置が使えなくなります。4年前にシャープが経営再建のため1億円にまで減資して中小企業の特例措置の適用を受けようとした(批判が相次いだため取りやめた)くらいですから、この影響はかなり大きいのです!
大きく見ると、会社の資金調達の種類は2種類しかなく、返さなくていいお金(資本金など=自己資本)と、返さないといけないお金(借入金など=他人資本)に分けられます。資本金が増えるということは、会社にとっては返さなくていいお金が増えることになり、それだけ財務基盤が強化されることになります。増資の方法には、追加で資金を入れる方法(有償増資)以外に、お金を入れないで会計処理上だけで資本金を増やす方法(無償増資)、また無償増資の方法の一つとして、借入金を資本金に組み入れる方法(DESという)などもあります。
増資の時に注意しないといけないのは、知らず知らずのうちに株主間で贈与関係が発生し、贈与税を払わないといけなくなることがあるということです。例えば100株=100万円を株主Aさんが出資して会社を新しく作って、その会社が儲かって1,000万円の利益を出したとします。その後Bさんが、俺にも出資させてくれと、Aさんと同条件で100株=100万円を追加出資したとします。
これでBさんには53万円の贈与税がかかってしまいます(AさんとBさんが親子でないと仮定)。なぜだか分かりますか・・?
Bさんが出資する直前、Aさんの所有する100株は、出資金100万円+利益1,000万円=1,100万円の価値(時価)があります。ここでBさんが出資すると、会社の価値総額は1,100万円+Bさん出資金100万円=1,200万円。この時点で株主はAさん100株、Bさん100株なので、合計200株。AさんとBさんの株式価値はそれぞれ1,200万円×100/200株=600万円になります。
Aさんの株式の価値は1,100万円から600万円に減ってしまいました。一方Bさんは100万円出資しただけなのに600万円の価値を手にしました。これは実質AさんからBさんに500万円の価値が移転したということになり、「実質的に贈与があった」とみなされるからです。そうならないためには、Bさんは100株を1,100万円で取得しなければいけません。
資本金が増えると、法人の納税額にも影響が出ます。ひとつは法人市民税の均等割です。資本金が1,000万円以下ですと年額5~12万円、それ以上1億円以下で13~15万円、1億円超10億円以下で16~40万円、といった具合です(広島市の場合。厳密には資本金「等」で判定)。
また資本金が1億円を超えると、法人税法上(中小企業ではなく)大法人とみなされます。こうなると、軽減税率の不適用、交際費の一部損金不算入、留保金課税、30万円未満の資産の全額損金算入特例の不適用、繰越欠損金の一部使用不可、法人事業税の外形標準課税適用(赤字でも事業税が発生する)など、さまざまな特例措置が使えなくなります。4年前にシャープが経営再建のため1億円にまで減資して中小企業の特例措置の適用を受けようとした(批判が相次いだため取りやめた)くらいですから、この影響はかなり大きいのです!
103万円の壁は崩壊!現状を正確に確認
2019/08/01 20:11:13 節税
コメント (0)
「年収を103万円以内に抑えないと、主人の扶養から外れたら大変・・」奥様がパートで働く場合によく言われるセリフです。現在、これは正しくなくなっています。
「扶養」には2種類あり、その要件が異なります。(1)税金の扶養から外れるのが年収103万円(通勤費除く)以下、(2)社会保険等の扶養から外れるのが130万円(通勤費含む)以下、になります(給与収入のみの場合)。それ自体は変わっていないのですが、(1)には続きがあります。
まず、年収103万円以下の場合は、ご主人は配偶者控除38万円が取れます。これは変わりません。そして103万円を超えた場合、確かに配偶者控除は取れなくなりますが、その替わりに配偶者特別控除が取れます。しかも税制改正により、平成30年以降は年収150万円以下の場合は配偶者特別控除が38万円取れます。つまり奥様の年収150万円までは、ご主人は控除が38万円(変わらず)取れますので、103万円の壁は150万円に替わっていた!と言えます。ただし社会保険等の130万円の壁は変わらず存在します。社会保険等を奥様が別途負担するようになると夫婦の手取り合計が下がりますので、結局130万円の壁は越えてはいけないということになります。
また同時に配偶者特別控除には所得制限が設けられ、ご主人の所得金額が900万円超では配偶者特別控除が減額され、所得金額1,000万円超(給与収入のみの場合、1,220万円超)で控除が受けられなくなりました。
この配偶者特別控除の改正は平成30年からですが、この類の給与・扶養関係の控除を引き下げる動きは近年細かく少しずつ施行されています。さらに令和2年からはこのような改正もあります。
令和2年からの給与所得控除(基本は増税)
→ (1)一律10万円引き下げ
(2)控除を受けられる給与収入の上限を850万円に引き下げ(現行は1,000万円)
(3)控除額の上限を195万円に引き下げ(現行は220万円)
(4)給与収入から850万円を控除した金額の10%を、給与所得から控除(ただし本人または
扶養親族が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族がいる場合のみ)
令和2年からの基礎控除
→ (1)一律10万円引き上げ(ここだけ減税。ただし給与所得控除の(1)で行って来い・・)
(2)所得金額が2,400万円超の人は引き下げ、2,500万円超で0円に
そして上記2つの改正に伴い、扶養親族の合計所得要件を48万円以下(現行38万円以下)に引き上げました。ただし給与所得控除の引き下げがありますので、扶養親族の給与収入の上限は48万円+(65-10)万円=103万円で変わりません(^_^;)
それにしても、基礎控除までいじくるのか~という感じです。ああややこしいなあ(>_<)
「扶養」には2種類あり、その要件が異なります。(1)税金の扶養から外れるのが年収103万円(通勤費除く)以下、(2)社会保険等の扶養から外れるのが130万円(通勤費含む)以下、になります(給与収入のみの場合)。それ自体は変わっていないのですが、(1)には続きがあります。
まず、年収103万円以下の場合は、ご主人は配偶者控除38万円が取れます。これは変わりません。そして103万円を超えた場合、確かに配偶者控除は取れなくなりますが、その替わりに配偶者特別控除が取れます。しかも税制改正により、平成30年以降は年収150万円以下の場合は配偶者特別控除が38万円取れます。つまり奥様の年収150万円までは、ご主人は控除が38万円(変わらず)取れますので、103万円の壁は150万円に替わっていた!と言えます。ただし社会保険等の130万円の壁は変わらず存在します。社会保険等を奥様が別途負担するようになると夫婦の手取り合計が下がりますので、結局130万円の壁は越えてはいけないということになります。
また同時に配偶者特別控除には所得制限が設けられ、ご主人の所得金額が900万円超では配偶者特別控除が減額され、所得金額1,000万円超(給与収入のみの場合、1,220万円超)で控除が受けられなくなりました。
この配偶者特別控除の改正は平成30年からですが、この類の給与・扶養関係の控除を引き下げる動きは近年細かく少しずつ施行されています。さらに令和2年からはこのような改正もあります。
令和2年からの給与所得控除(基本は増税)
→ (1)一律10万円引き下げ
(2)控除を受けられる給与収入の上限を850万円に引き下げ(現行は1,000万円)
(3)控除額の上限を195万円に引き下げ(現行は220万円)
(4)給与収入から850万円を控除した金額の10%を、給与所得から控除(ただし本人または
扶養親族が特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族がいる場合のみ)
令和2年からの基礎控除
→ (1)一律10万円引き上げ(ここだけ減税。ただし給与所得控除の(1)で行って来い・・)
(2)所得金額が2,400万円超の人は引き下げ、2,500万円超で0円に
そして上記2つの改正に伴い、扶養親族の合計所得要件を48万円以下(現行38万円以下)に引き上げました。ただし給与所得控除の引き下げがありますので、扶養親族の給与収入の上限は48万円+(65-10)万円=103万円で変わりません(^_^;)
それにしても、基礎控除までいじくるのか~という感じです。ああややこしいなあ(>_<)
- < 前
- Page 1 / 4
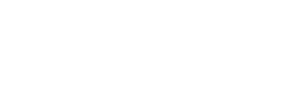

 RSS 2.0
RSS 2.0