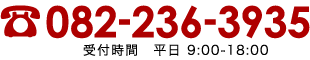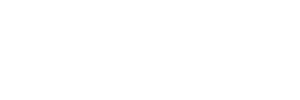ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
これからはPDCAではなく、DCAPで
2023/06/24 15:49:34 経営
コメント (0)
PDCAという経営用語があります。とても有名なのでご存知の方も多いと思いますが、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の順番で業務を行い、ActionからまたPlanに戻って業務を循環させることで、継続的な業務改善を促す手法です。
綿密な経営計画を作成し、それに沿って業務を実行する。その業務結果を測定値や経営成績という形で評価し、数値目標等に届かなかった部分の改善点を洗い出し、次の計画に繋げる・・。その流れ自体はとても合理的だと思いますが、私にはひとつ疑問があります。
最初にいきなり「綿密な計画」って立てれますかね?私は自信がありません。高すぎる無謀な売上目標や、逆にほぼ現状維持でも達成できちゃう低いハードルでは意味がないばかりか、その後の実行内容がおかしくなってしまいます。なによりこの早い時代の流れの中、正確に未来を予測して計画を立てるなんて不可能です。誰がこのコロナ禍の時代が来ることを予測できましたか?
それに、もしその計画が上司や金融機関が作成したものだとして、その内容が自分にとって腑に落ちないものだったら・・。やる気になりますかね?人間は自分が腑に落ちないままで行動しても、結果を出せない生き物だと思います。
私は、今の時代はDoから始めるべきだと思います。まずやってみる!そしてやってみた結果を評価する、うまくいかなかった部分の改善点を考える。・・ここまでの材料が揃ってから、初めて計画をたてるのです。五里霧中のなかで頭の中だけで立てた計画と、実際にやってみたことで得られた結果の材料をもとにたてた計画、どちらの精度が高いか、言うまでもないですよね。
何より自分の行動の結果をもとにした計画なので、とっても腑に落ちると思います。やる気も出ますし、結果もきっと違ってきます。つまりPDCAの順番で回すのではなく、DCAPの順番で回すのです。まあ回り初めてしまえばどちらも順番は同じなのですが、DCAPのほうはセンスメイキング(←気になる方はググってみて下さい)という考え方に近くなると思います。
注意しないといけないのは、いきなりDoから始めるって、場合によっては無謀なケースもあると思います。失敗しても引き返せる、失敗時の損失は許容範囲内で収まるようにしておく、というリスクヘッジは必ず必要になります。あとは行動を重視するあまり、自分の行動だけを信じちゃう、自分しか信用できない!という感覚になってしまうのも危険です。偏りすぎないバランス感覚も持つことも必要だと思います。
綿密な経営計画を作成し、それに沿って業務を実行する。その業務結果を測定値や経営成績という形で評価し、数値目標等に届かなかった部分の改善点を洗い出し、次の計画に繋げる・・。その流れ自体はとても合理的だと思いますが、私にはひとつ疑問があります。
最初にいきなり「綿密な計画」って立てれますかね?私は自信がありません。高すぎる無謀な売上目標や、逆にほぼ現状維持でも達成できちゃう低いハードルでは意味がないばかりか、その後の実行内容がおかしくなってしまいます。なによりこの早い時代の流れの中、正確に未来を予測して計画を立てるなんて不可能です。誰がこのコロナ禍の時代が来ることを予測できましたか?
それに、もしその計画が上司や金融機関が作成したものだとして、その内容が自分にとって腑に落ちないものだったら・・。やる気になりますかね?人間は自分が腑に落ちないままで行動しても、結果を出せない生き物だと思います。
私は、今の時代はDoから始めるべきだと思います。まずやってみる!そしてやってみた結果を評価する、うまくいかなかった部分の改善点を考える。・・ここまでの材料が揃ってから、初めて計画をたてるのです。五里霧中のなかで頭の中だけで立てた計画と、実際にやってみたことで得られた結果の材料をもとにたてた計画、どちらの精度が高いか、言うまでもないですよね。
何より自分の行動の結果をもとにした計画なので、とっても腑に落ちると思います。やる気も出ますし、結果もきっと違ってきます。つまりPDCAの順番で回すのではなく、DCAPの順番で回すのです。まあ回り初めてしまえばどちらも順番は同じなのですが、DCAPのほうはセンスメイキング(←気になる方はググってみて下さい)という考え方に近くなると思います。
注意しないといけないのは、いきなりDoから始めるって、場合によっては無謀なケースもあると思います。失敗しても引き返せる、失敗時の損失は許容範囲内で収まるようにしておく、というリスクヘッジは必ず必要になります。あとは行動を重視するあまり、自分の行動だけを信じちゃう、自分しか信用できない!という感覚になってしまうのも危険です。偏りすぎないバランス感覚も持つことも必要だと思います。
ライバルとは、もう切磋琢磨しない
2023/05/01 14:36:57 経営
コメント (0)
受験勉強やスポーツにおいて、仲間と切磋琢磨することでお互いが成長するのはとても素晴らしいことだと思います。この考えは経営にも応用され(レッドクイーン理論と言います)、高度成長期ではライバル社と製品の品質向上を競い合うことで、結果として日本製品のネームバリューが上がり、日本企業は世界市場を席巻しました。
しかし時代は移りゆき、ライバルを意識するあまり小さな改変しかできなくなったり、ライバルの真似ばかりしてなんとか自分のシェアを減らさないようにする、といったことに終始するようになってしまいました。その結果IT時代の到来などの大きな変化に対応できなくなり、例えば日本企業がガラケーの細かいスペック競争に気を取られているうちに、スマホ市場で世界から駆逐されてしまいました。時代の移り変わりのスピードが急激になった現在では、ライバルとの切磋琢磨では大きな環境変化に対応できないのです。
もちろん切磋琢磨そのものに意味がなくなったわけではありません。これからは自分の未来のビジョン、つまり「したい・なりたい自分」を想い描き、その未来の自分と切磋琢磨すべき時代に突入しているのだと思います。
しかし時代は移りゆき、ライバルを意識するあまり小さな改変しかできなくなったり、ライバルの真似ばかりしてなんとか自分のシェアを減らさないようにする、といったことに終始するようになってしまいました。その結果IT時代の到来などの大きな変化に対応できなくなり、例えば日本企業がガラケーの細かいスペック競争に気を取られているうちに、スマホ市場で世界から駆逐されてしまいました。時代の移り変わりのスピードが急激になった現在では、ライバルとの切磋琢磨では大きな環境変化に対応できないのです。
もちろん切磋琢磨そのものに意味がなくなったわけではありません。これからは自分の未来のビジョン、つまり「したい・なりたい自分」を想い描き、その未来の自分と切磋琢磨すべき時代に突入しているのだと思います。
二宮尊徳の言葉から思うことあれこれ
2023/02/01 17:44:22 経営
コメント (0)
突然ですが、二宮尊徳(二宮金次郎)をご存知ですか?薪(まき)を背負いながら本を読んでいる銅像が小学校にありましたよね、あの方です。「勤勉」のイメージはあるものの、何をした人か知らないという方も多いと思いますが、江戸時代後期に荒れた農村の復興を指導し、また道徳と経済の両立を説いた「報徳思想」を唱える思想家でした。その二宮尊徳の残した言葉の中に、こんな名言があります。
「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」
かなりストレートかつ本質をついた言葉だと思います。企業・事業者の目的は利益を出すことであるのに間違いはありませんが、経営理念もなくただただ顧客から売上を搾取するような行為は犯罪と同じだ、と断じています。顧客に、ひいては社会に役立つ商品・サービスを提供し、それに見合う対価を得ながら発展することこそ企業の存在意義だということですね。企業が継続的に発展していくには、顧客・社会に貢献するという視点・観点を忘れることがあってはならないと私も思います。
また後半の言葉も厳しいですね。いくら顧客・社会のためという理念があっても、必要以上な安売りや過剰サービスで企業が疲弊し、利益を残すことができなければ永続的に良質な商品・サービスが提供できなくなり、結果的に顧客・社会を裏切ることになる。永続的な実現ができないような経済活動は結局寝言(=意味がない)と断じています。
ところで、最近賃上げの話題が多くなっております。ファーストリテイリング(ユニクロ)がこの春から最大40%の賃上げを行うなど、大手企業で賃上げの動きが相次いでいます。たまった内部留保を活用して、有能な人材を確保していくという動きは日本全体にとっても良いことだと思います。賃金が上がる→購買意欲が増える→企業の業績が良くなる→賃金が上がる→・・の好循環がなかったから、日本は30年間経済成長しなかったわけですから。
一方中小企業はどうでしょうか?賃上げできますか?どうしても必要な人材には(引き止めという意味も含めて)賃上げが必要になってくると思います。そうなると、企業に必須でない人材の賃上げまでする余力がない中小企業では、給与格差が拡大していくのかなと思います。
企業としては、従業員の給与を絞って絞って利益を搾取するようでは最終的には必要な人材まで流出することになり、継続的な発展はないでしょう。かといって大盤振る舞いばかりしていては資金がもたなくなり、結局最終的には職員を失業させてしまうことになるかもしれません。まさに二宮尊徳の言う通りになってしまいます。給与体系の見直しが必要でしょうし、人材配置や社内業務の合理化、また商品・サービスの差別化など、やるべきことをやる企業とやらない企業との格差もまた、拡大していくのだと思います。
「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」
かなりストレートかつ本質をついた言葉だと思います。企業・事業者の目的は利益を出すことであるのに間違いはありませんが、経営理念もなくただただ顧客から売上を搾取するような行為は犯罪と同じだ、と断じています。顧客に、ひいては社会に役立つ商品・サービスを提供し、それに見合う対価を得ながら発展することこそ企業の存在意義だということですね。企業が継続的に発展していくには、顧客・社会に貢献するという視点・観点を忘れることがあってはならないと私も思います。
また後半の言葉も厳しいですね。いくら顧客・社会のためという理念があっても、必要以上な安売りや過剰サービスで企業が疲弊し、利益を残すことができなければ永続的に良質な商品・サービスが提供できなくなり、結果的に顧客・社会を裏切ることになる。永続的な実現ができないような経済活動は結局寝言(=意味がない)と断じています。
ところで、最近賃上げの話題が多くなっております。ファーストリテイリング(ユニクロ)がこの春から最大40%の賃上げを行うなど、大手企業で賃上げの動きが相次いでいます。たまった内部留保を活用して、有能な人材を確保していくという動きは日本全体にとっても良いことだと思います。賃金が上がる→購買意欲が増える→企業の業績が良くなる→賃金が上がる→・・の好循環がなかったから、日本は30年間経済成長しなかったわけですから。
一方中小企業はどうでしょうか?賃上げできますか?どうしても必要な人材には(引き止めという意味も含めて)賃上げが必要になってくると思います。そうなると、企業に必須でない人材の賃上げまでする余力がない中小企業では、給与格差が拡大していくのかなと思います。
企業としては、従業員の給与を絞って絞って利益を搾取するようでは最終的には必要な人材まで流出することになり、継続的な発展はないでしょう。かといって大盤振る舞いばかりしていては資金がもたなくなり、結局最終的には職員を失業させてしまうことになるかもしれません。まさに二宮尊徳の言う通りになってしまいます。給与体系の見直しが必要でしょうし、人材配置や社内業務の合理化、また商品・サービスの差別化など、やるべきことをやる企業とやらない企業との格差もまた、拡大していくのだと思います。
広島県独自の月次支援金もスタート
2021/06/24 16:10:00 経営
コメント (0)
国の月次支援金が6月16日からスタートしたことは前回お伝えいたしましたが、広島県独自でも「がんばる中小企業者月次支援金」が6月21日より始まっております。支給条件等は基本的には国の月次支援金と同じですが、広島県のものは5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて30%以上減少した場合も対象としております(国の月次支援金は50%以上減少)。そのため、国の月次支援金が対象外の場合でも県の支援金が対象になる場合があります。また50%以上減少した場合には国と県の重複支給を受けることも可能です。支給額は国のものと同様に、中小法人は月20万円、個人事業主は月10万円が上限です。
申請は5月分は6/21~8/20、6月分は7/1~8/31となっております。また国のものと異なり、申請には登録確認機関の事前確認は必要ありません。なお広島県以外でも独自の支援金を発表しているところがありますので、ご確認いただければと思います。
申請は5月分は6/21~8/20、6月分は7/1~8/31となっております。また国のものと異なり、申請には登録確認機関の事前確認は必要ありません。なお広島県以外でも独自の支援金を発表しているところがありますので、ご確認いただければと思います。
広島県等も月次支援金の対象に
2021/06/01 12:11:39 経営
コメント (0)
広島県等でも5月16日に緊急事態宣言が発令され、6月20日まで延長となっております。飲食店等では休業要請に伴う協力金が県から支給されますが、それ以外の業種でも緊急事態宣言に伴う影響を受け、5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて50%以上減少した場合は、月次支援金の申請ができます。給付額上限は各月ごとに法人20万円、個人事業者10万円です。各月分ごとに別途申請する必要があります。協力金との重複申請はできません。
対象業種は基本的には問わないとされていますが、売上計上時期をずらして50%以下にしても支給しませんとはっきり書かれています。このあたりは、持続化給付金で不正受給が相次いだ反省から、あらかじめそういった申請を牽制している感があります。
申請は5月分は6月中下旬~8月中下旬、6月分は7/1~8/31となっています。月次支援金ホームページの開設自体が6月中旬の開設予定ということです。また申請には登録確認機関の事前確認が必要ですが、当事務所は登録確認機関として登録されております。顧問先様は、事前確認のみでしたら無料でさせていただきます(申請手続き全てを代行させていただく場合は有料となります)。申請をご検討される際には、各担当者にご相談いただければと思います。
対象業種は基本的には問わないとされていますが、売上計上時期をずらして50%以下にしても支給しませんとはっきり書かれています。このあたりは、持続化給付金で不正受給が相次いだ反省から、あらかじめそういった申請を牽制している感があります。
申請は5月分は6月中下旬~8月中下旬、6月分は7/1~8/31となっています。月次支援金ホームページの開設自体が6月中旬の開設予定ということです。また申請には登録確認機関の事前確認が必要ですが、当事務所は登録確認機関として登録されております。顧問先様は、事前確認のみでしたら無料でさせていただきます(申請手続き全てを代行させていただく場合は有料となります)。申請をご検討される際には、各担当者にご相談いただければと思います。
- < 前
- Page 1 / 5
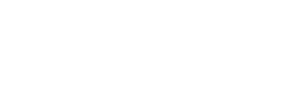

 RSS 2.0
RSS 2.0