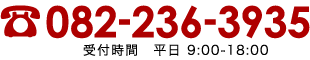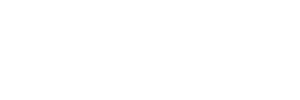ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
選択と集中で、頑張れ、日本!
2026/02/02 16:54:48 経済一般
コメント (0)
異例の短期決戦と呼ばれる選挙期間に入っております。現時点(令和8年2月2日)ではその結果はまだ出ておりませんし、政治的な思想・思惑はいろいろあると思いますが、17の戦略分野に重点投資する「選択と集中」という考え方は、会社経営においても基本的かつ重要な戦略の方法だと言えます。
ただ中小企業だと「17分野」は多すぎるので、多くても3~5つ、もしくは1点集中に成長分野を絞り込み、そこに会社のリソースの少なくとも7割以上は割くというバランスがいいのではないでしょうか。
日本の戦略分野で私が最も気になっているのは「海洋」の分野で、特にレアアース泥の掘削です。レアアースとは簡単に言うと「特別な性質を持った17種類の金属の総称」で、これを少し混ぜるだけでハイテク製品の性能を劇的にアップさせる力があります。自動車、スマホなどに欠かせない「現代産業のビタミン」という呼び名もあります。逆にレアアースが手に入らなくなると、日本の産業は心肺停止状態に陥るとも言われます。
そのレアアースですが、現在中国が世界の生産量の大部分を占めており、日本も約60~70%(一部の金属はほぼ100%)を中国に依存していますが、ご存知の通り高市首相の「台湾有事は日本にとっての存立危機事態になり得る」という発言をきっかけに、中国がレアアースの輸出禁止措置をちらつかせてきました。
そんな中、2月1日に日本が南鳥島沖の水深約6,000メートルからレアアース泥を引き上げることに成功しました。南鳥島沖には日本の需要の数百年分のレアアース資源が眠っていることが以前からわかっていましたが、あまりに深すぎて技術的に引き上げは不可能だと言われていました。ものすごい水圧のかかる6,000メートルの深海の底にまでパイプを垂らし、波風や潮の流れを常に読む(数メートル波に流されただけでパイプが折れてしまう)必要があるからです。AIにその難しさを比喩してもらうと、「東京スカイツリー10本分の長さのある超長いストローを海に垂らし、揺れる船の上から海底にあるタピオカを吸い込む」「地上600メートルのヘリコプターから、地面に置かれた針の穴に糸を通す」などの回答が出てきました。こんな難しいことを世界で初めて成功させられるだけの技術力が、日本にはあるということです。
もちろんまだまだ問題も多いようで、そんな深海から引き上げるのはコストがかかりすぎて中国との価格競争では太刀打ちできないこと、またレアアースを泥や岩石から溶かし出す際に使う強力な薬品が環境汚染につながること、などです。とはいえこれらの課題をもし克服できれば、日本は常に資源を他国からの輸入に依存している状況から一転、資源大国になれる可能性を秘めているわけです。
他にも日本独自の、世界に誇れる技術・強みはたくさんあります。そんな強みをもっともっと「選択と集中」で活かしていけるといいですよね。頑張れ、日本!
ただ中小企業だと「17分野」は多すぎるので、多くても3~5つ、もしくは1点集中に成長分野を絞り込み、そこに会社のリソースの少なくとも7割以上は割くというバランスがいいのではないでしょうか。
日本の戦略分野で私が最も気になっているのは「海洋」の分野で、特にレアアース泥の掘削です。レアアースとは簡単に言うと「特別な性質を持った17種類の金属の総称」で、これを少し混ぜるだけでハイテク製品の性能を劇的にアップさせる力があります。自動車、スマホなどに欠かせない「現代産業のビタミン」という呼び名もあります。逆にレアアースが手に入らなくなると、日本の産業は心肺停止状態に陥るとも言われます。
そのレアアースですが、現在中国が世界の生産量の大部分を占めており、日本も約60~70%(一部の金属はほぼ100%)を中国に依存していますが、ご存知の通り高市首相の「台湾有事は日本にとっての存立危機事態になり得る」という発言をきっかけに、中国がレアアースの輸出禁止措置をちらつかせてきました。
そんな中、2月1日に日本が南鳥島沖の水深約6,000メートルからレアアース泥を引き上げることに成功しました。南鳥島沖には日本の需要の数百年分のレアアース資源が眠っていることが以前からわかっていましたが、あまりに深すぎて技術的に引き上げは不可能だと言われていました。ものすごい水圧のかかる6,000メートルの深海の底にまでパイプを垂らし、波風や潮の流れを常に読む(数メートル波に流されただけでパイプが折れてしまう)必要があるからです。AIにその難しさを比喩してもらうと、「東京スカイツリー10本分の長さのある超長いストローを海に垂らし、揺れる船の上から海底にあるタピオカを吸い込む」「地上600メートルのヘリコプターから、地面に置かれた針の穴に糸を通す」などの回答が出てきました。こんな難しいことを世界で初めて成功させられるだけの技術力が、日本にはあるということです。
もちろんまだまだ問題も多いようで、そんな深海から引き上げるのはコストがかかりすぎて中国との価格競争では太刀打ちできないこと、またレアアースを泥や岩石から溶かし出す際に使う強力な薬品が環境汚染につながること、などです。とはいえこれらの課題をもし克服できれば、日本は常に資源を他国からの輸入に依存している状況から一転、資源大国になれる可能性を秘めているわけです。
他にも日本独自の、世界に誇れる技術・強みはたくさんあります。そんな強みをもっともっと「選択と集中」で活かしていけるといいですよね。頑張れ、日本!
令和8年度税制改正大綱の内容を解説!
2026/01/05 18:10:18 税制改正
コメント (0)
令和8年度の税制改正大綱が令和7年12月26日に閣議決定されました。早速121ページある大綱から気になったものをピックアップしていきます。
(1)年収の壁と扶養控除範囲の見直し
「年収の壁」とはいくらまでの収入なら所得税がかからないかというラインのことで、給与収入のみの場合の金額が令和7年から103万円→160万円に改正されていました。これが令和8年から178万円に再度改正されます。基礎控除の最大額が95万円から104万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に改正されたため、104+74=178万円に年収の壁が変わりました(ただし令和10年以降はまた見直される予定)。なおこの年収の壁はあくまで所得税に関してなので、住民税は108万円からかかります。
またこの年収の壁はあくまで「本人に」所得税がかからないラインなので、178万円までなら税金上の扶養に入れるという意味ではありません。扶養に入れるのは給与収入の場合、基礎控除(本則)62万円+給与所得控除(特例を除く金額)69万円=131万円まで(令和7年は123万円まで、それ以前は103万円まで)です。社会保険の扶養判定も130万円ですので、ざっくりと「税金も社会保険も130万円まで」を目安に考えてもいいでしょう。
(2)暗号資産の課税見直し
暗号資産への課税が20%申告分離課税になります(金商法改正の翌年1月1日から)。現状の総合課税では最大55%課税されるため利益確定をためらっていた方も多いと思われますが、今後は上場株式と同様の課税になる(3年間の損失繰越控除も使える)ため、より取引しやすくなったと言えます。
ただし特定口座の制度はないので、源泉徴収はされないため今後も必ず確定申告は必要になります。また確定ではありませんが、国外転出時課税の対象になる(対象資産を1億円以上所有していた場合(売却していなくても)出国時に含み益に対して課税される)、国外取引所で取引したものは分離課税の対象から外される、という内容がセットになる可能性が高いです。
(3)免税事業者からの仕入税額控除の特例の改正(インボイス関連)
免税事業者に支払った経費につき消費税部分の80%を控除できる特例が令和8年9月で終わりますが、その後の特例スケジュールが変更になり、令和10年9月まで70%控除、令和12年9月まで50%控除、令和13年9月まで30%控除となりました(改正前は令和11年9月まで50%控除のみ)。また元免税事業者の納税額を軽減するいわゆる「2割特例」についても令和8年9月で終わりますが、その後令和10年9月まで「3割特例」が追加されます。
(4)少額減価償却資産の特例の改正
青色事業者が全額減価償却費で落とせる固定資産の額が30万円→40万円未満に。ただし年間合計300万円までが上限、という要件はそのままです。大綱には明記されていませんが、おそらく令和8年4月から適用されると思われます。
(1)年収の壁と扶養控除範囲の見直し
「年収の壁」とはいくらまでの収入なら所得税がかからないかというラインのことで、給与収入のみの場合の金額が令和7年から103万円→160万円に改正されていました。これが令和8年から178万円に再度改正されます。基礎控除の最大額が95万円から104万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円から74万円に改正されたため、104+74=178万円に年収の壁が変わりました(ただし令和10年以降はまた見直される予定)。なおこの年収の壁はあくまで所得税に関してなので、住民税は108万円からかかります。
またこの年収の壁はあくまで「本人に」所得税がかからないラインなので、178万円までなら税金上の扶養に入れるという意味ではありません。扶養に入れるのは給与収入の場合、基礎控除(本則)62万円+給与所得控除(特例を除く金額)69万円=131万円まで(令和7年は123万円まで、それ以前は103万円まで)です。社会保険の扶養判定も130万円ですので、ざっくりと「税金も社会保険も130万円まで」を目安に考えてもいいでしょう。
(2)暗号資産の課税見直し
暗号資産への課税が20%申告分離課税になります(金商法改正の翌年1月1日から)。現状の総合課税では最大55%課税されるため利益確定をためらっていた方も多いと思われますが、今後は上場株式と同様の課税になる(3年間の損失繰越控除も使える)ため、より取引しやすくなったと言えます。
ただし特定口座の制度はないので、源泉徴収はされないため今後も必ず確定申告は必要になります。また確定ではありませんが、国外転出時課税の対象になる(対象資産を1億円以上所有していた場合(売却していなくても)出国時に含み益に対して課税される)、国外取引所で取引したものは分離課税の対象から外される、という内容がセットになる可能性が高いです。
(3)免税事業者からの仕入税額控除の特例の改正(インボイス関連)
免税事業者に支払った経費につき消費税部分の80%を控除できる特例が令和8年9月で終わりますが、その後の特例スケジュールが変更になり、令和10年9月まで70%控除、令和12年9月まで50%控除、令和13年9月まで30%控除となりました(改正前は令和11年9月まで50%控除のみ)。また元免税事業者の納税額を軽減するいわゆる「2割特例」についても令和8年9月で終わりますが、その後令和10年9月まで「3割特例」が追加されます。
(4)少額減価償却資産の特例の改正
青色事業者が全額減価償却費で落とせる固定資産の額が30万円→40万円未満に。ただし年間合計300万円までが上限、という要件はそのままです。大綱には明記されていませんが、おそらく令和8年4月から適用されると思われます。
優遇されている退職所得の税金
2025/12/01 10:29:15 節税
コメント (0)
退職所得とは具体的には企業からの退職金、小規模共済の一時金、iDeCoの一時金などがこれにあたりますが、退職所得は給与所得などと比べて大幅に税金が軽減されるように優遇されています。退職所得の計算は、退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2となっており、まず勤務年数や加入年数が20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年超の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)の金額が退職所得控除として差し引かれます。要は1年ごとに40万円、70万円が追加で非課税になっていきます。その上残った金額が2分の1されますので、残額の半分も非課税になる、ということになります。
さらに退職所得は「分離課税による累進課税」になります。どういうことかと言うと、例えば給与所得等が3,000万円と退職所得が300万円あった場合に、給与所得等は累進課税により40%の所得税が課されますが、退職所得は他の所得金額は無視して300万円に対する累進税率(この場合は10%)の所得税率しかかかりません。このように退職所得には①退職所得控除、②2分の1課税、③分離課税による累進課税という三重の優遇措置があるわけです(一部例外はあり)。
そのため現役世代にとって退職金を準備することは、「将来の備え」と「節税」の両立になります。iDeCoは65歳未満の方は原則誰でも加入できますので、会社の退職金にプラスして加入することで掛金を毎年の所得控除にしつつ、将来安い税額で一時金を受け取ることができます。個人事業主や法人役員ですと小規模共済をつかって退職金準備ができますし、法人役員はさらに自身の退職金原資を生命保険や倒産防止共済をつかって積み立てることで社会保険料の節約にもつながります。
注意点としては退職所得控除には重複期間の調整というものがあり、退職金を受け取った際にその年の4年前までに他の退職金を受け取っていた場合は、前回の勤続期間・加入期間と重複している期間の退職所得控除が原則受けられなくなります。この重複期間の調整は少し複雑なので詳細は割愛しますが、退職金を受け取る際は前回の退職金から5年以上空いているかどうかを意識しておく必要があります。
さらに「老後資金は自分自身でも準備せよ」ということで広がっていったはずのiDeCoにいたっては徐々に改悪が続いており、令和8以降はiDeCo→退職金の順番に受け取る場合は10年以上、退職金→iDeCoの順番に受け取る場合は20年以上空いていないと後で受け取ったほうの退職所得控除が調整されます。10年や20年空けるのは実質ほぼ不可能であり、「iDeCoは広めるが税金の優遇はしません」という日本政府からのメッセージでしょう。
さらに退職所得は「分離課税による累進課税」になります。どういうことかと言うと、例えば給与所得等が3,000万円と退職所得が300万円あった場合に、給与所得等は累進課税により40%の所得税が課されますが、退職所得は他の所得金額は無視して300万円に対する累進税率(この場合は10%)の所得税率しかかかりません。このように退職所得には①退職所得控除、②2分の1課税、③分離課税による累進課税という三重の優遇措置があるわけです(一部例外はあり)。
そのため現役世代にとって退職金を準備することは、「将来の備え」と「節税」の両立になります。iDeCoは65歳未満の方は原則誰でも加入できますので、会社の退職金にプラスして加入することで掛金を毎年の所得控除にしつつ、将来安い税額で一時金を受け取ることができます。個人事業主や法人役員ですと小規模共済をつかって退職金準備ができますし、法人役員はさらに自身の退職金原資を生命保険や倒産防止共済をつかって積み立てることで社会保険料の節約にもつながります。
注意点としては退職所得控除には重複期間の調整というものがあり、退職金を受け取った際にその年の4年前までに他の退職金を受け取っていた場合は、前回の勤続期間・加入期間と重複している期間の退職所得控除が原則受けられなくなります。この重複期間の調整は少し複雑なので詳細は割愛しますが、退職金を受け取る際は前回の退職金から5年以上空いているかどうかを意識しておく必要があります。
さらに「老後資金は自分自身でも準備せよ」ということで広がっていったはずのiDeCoにいたっては徐々に改悪が続いており、令和8以降はiDeCo→退職金の順番に受け取る場合は10年以上、退職金→iDeCoの順番に受け取る場合は20年以上空いていないと後で受け取ったほうの退職所得控除が調整されます。10年や20年空けるのは実質ほぼ不可能であり、「iDeCoは広めるが税金の優遇はしません」という日本政府からのメッセージでしょう。
金(ゴールド)暴騰!これもインフレの波なのか
2025/11/04 11:58:12 株式投資
コメント (0)
金(ゴールド)価格の上昇が止まりません。金は株式や債券と違って発行体の経営難で紙クズになる等のリスクがないので昔から安全資産として知られており、2019年ころから価格も少しずつ上昇していました。しかし今年の9月初めから価格は一気に上昇し、ピークを付けた10/17までの1ヶ月半ほどで価格はなんと約25%も上昇しました。そしてそんな声を聞いてか金を買い求める人は一気に増え、金販売大手の田中貴金属では、銀座本店前に5時間待ちの行列ができ、その後5gや10gなどの小型の金の製造加工が追いつかないため一時販売停止になった(R7.11.1現在も再開していない)というニュースまで出ました。また金だけでなく、銀やプラチナなどの価格も大きく上昇しました。
最近の上昇は異常すぎるにしても、なぜ金価格は上昇し続けているのでしょうか。一番大きな理由は、中国がアメリカ国債の保有を減らすために売却を続け、その資金で金を買って金保有量をどんどん増やしているからです。買いニーズが増えれば価格も上がるわけです。
ではなぜ中国がアメリカ国債を手放しているかと言うと、ロシアがウクライナに侵攻したことの対抗措置としてアメリカがロシアの米ドル資産を凍結したことが、中国にとって強い衝撃だったからだと言われています。理由はそれだけではないかもしれませんが、確かに2022年以降金の上昇カーブはより強くなっています。
ただ理由はそれだけではなく、ドルの信任が揺らいでいて、投資家がドルから金に資金を動かしていることも大きいようです。アメリカの財政赤字が拡大を続けていること、雇用悪化により利下げ傾向であること、戦争等の地政学リスク上昇していること、また世界的なインフレ傾向が続きそうなこと、これらの全てが「ドルを売って金を買う」原因になっています。
また円も同じことが言えると思います。ドルの信任が揺らいでいても円高ドル安にならないのは円も下落しているからで、今は「円安ドル安」の状態になっています。
相場的には、普段は金など買ったことが無い人まで行列を作って買いに並ぶというのは価格のピークであることが多いので、短期的には価格は今後落ち着くような気がします。しかし長期的には上記のような上昇理由が急に無くなるとは思えないので、資産の一部は金で持っておくという備えも必要かもしれませんね。
最近の上昇は異常すぎるにしても、なぜ金価格は上昇し続けているのでしょうか。一番大きな理由は、中国がアメリカ国債の保有を減らすために売却を続け、その資金で金を買って金保有量をどんどん増やしているからです。買いニーズが増えれば価格も上がるわけです。
ではなぜ中国がアメリカ国債を手放しているかと言うと、ロシアがウクライナに侵攻したことの対抗措置としてアメリカがロシアの米ドル資産を凍結したことが、中国にとって強い衝撃だったからだと言われています。理由はそれだけではないかもしれませんが、確かに2022年以降金の上昇カーブはより強くなっています。
ただ理由はそれだけではなく、ドルの信任が揺らいでいて、投資家がドルから金に資金を動かしていることも大きいようです。アメリカの財政赤字が拡大を続けていること、雇用悪化により利下げ傾向であること、戦争等の地政学リスク上昇していること、また世界的なインフレ傾向が続きそうなこと、これらの全てが「ドルを売って金を買う」原因になっています。
また円も同じことが言えると思います。ドルの信任が揺らいでいても円高ドル安にならないのは円も下落しているからで、今は「円安ドル安」の状態になっています。
相場的には、普段は金など買ったことが無い人まで行列を作って買いに並ぶというのは価格のピークであることが多いので、短期的には価格は今後落ち着くような気がします。しかし長期的には上記のような上昇理由が急に無くなるとは思えないので、資産の一部は金で持っておくという備えも必要かもしれませんね。
生成AIを使い倒す時代がやってきた
2025/10/01 16:34:25 経済一般
コメント (0)
アメリカのGAFAMのうちMeta、Amazon、Alphabet(グーグル)、Microsoftの4社で2025年だけでも約3,200億ドルをAI技術関連に投資するそうです。途方もない額ですが、もはや事業投資の意味だけではなく、世界中の情報、インフラの覇権を握ることで政治的・軍事的な影響力や支配も考えているのかもしれません。
そして一般的に生成AIが普及し始めたのは2023年ころからですが、厳密には「AI」と「生成AI」は意味や範囲が異なります。AIは人工知能やその技術の総称ですが、生成AIは、そのうちテキスト・画像・音声などの新しいデータを生成するAIのことを指します。メールの文章を自動作成したり、文章(プロンプト)から画像を作ったりするのが生成AIです。
その生成AIで有名なものはChatGPT、Gemini、Copilotなどですが、調べてみると結構たくさんの種類があるようですね。また無料版と有料版のものがあり、何百ページもの長文分析や画像解析、音声解析、ファイル分析などを行うのであれば有料版が必要になりますが、文章入力で回答をもらう、という用途が主であれば無料版でも充分そうです。
私も最近は、少し複雑な税務相談についてまず生成AIに回答してもらい、その回答を裏付けする形で関連法令などを確認していく、という使い方をしています。とっても優秀ですが、最新の改正内容についてはアップデートが充分でないのか、間違った回答が返ってくることもよくあります。「その部分は間違ってないですか」と再質問すると、「さすがですね!」と褒めてくれます(生成AIの種類によっては塩対応のものもあるらしい)が、再回答の内容も充分でなかったりするので、今のところ税務に関する信用度は80~90%位という感覚です。あくまで回答のたたき台として使う感じです。
また最近会計面で話題になっているのは、領収書を重ねてそれを1枚ずつめくる動画をGeminiに読み込ませると、経費精算に使えるような一覧表を自動作成してくれたり、複式簿記による会計仕訳を自動生成してくれるというものです。これが高精度でできてしまうと、AI-OCR対応の会計ソフトが要らなくなるかもしれません。AIを使いこなせない会計事務所は近い将来消滅してしまうのでは、と思いましたね。
生成AIの使い道は無限で、例えば自社の経営現況を詳しくプロンプト入力して、「5年後に年商10億円にするために必要な経営計画を、同業他社の傾向も踏まえて、マーケティング面、人事面、財務面を中心に立ててください」と質問すると、豊富な情報量を元に、精度の高い計画を立案してくれます。上場企業でも、自社でカスタマイズした生成AIの回答を元に新商品を開発したり、経営そのものを行っている会社があるくらいです。
ただあくまでも生成AIの提示するものは「提案」であり、それを元に思考し、決断し、行動するのは経営者自身です。ボスは社長であることに変わりない、ということさえ忘れなければ、生成AIはとても優秀なパートナー、アシスタントになってくれると思います。
生成AIは日進月歩でどんどん使い方も変わってくると思います。事業経営にもプライベートにもうまく活用して、人生を高めるものにしていきたいですね。
そして一般的に生成AIが普及し始めたのは2023年ころからですが、厳密には「AI」と「生成AI」は意味や範囲が異なります。AIは人工知能やその技術の総称ですが、生成AIは、そのうちテキスト・画像・音声などの新しいデータを生成するAIのことを指します。メールの文章を自動作成したり、文章(プロンプト)から画像を作ったりするのが生成AIです。
その生成AIで有名なものはChatGPT、Gemini、Copilotなどですが、調べてみると結構たくさんの種類があるようですね。また無料版と有料版のものがあり、何百ページもの長文分析や画像解析、音声解析、ファイル分析などを行うのであれば有料版が必要になりますが、文章入力で回答をもらう、という用途が主であれば無料版でも充分そうです。
私も最近は、少し複雑な税務相談についてまず生成AIに回答してもらい、その回答を裏付けする形で関連法令などを確認していく、という使い方をしています。とっても優秀ですが、最新の改正内容についてはアップデートが充分でないのか、間違った回答が返ってくることもよくあります。「その部分は間違ってないですか」と再質問すると、「さすがですね!」と褒めてくれます(生成AIの種類によっては塩対応のものもあるらしい)が、再回答の内容も充分でなかったりするので、今のところ税務に関する信用度は80~90%位という感覚です。あくまで回答のたたき台として使う感じです。
また最近会計面で話題になっているのは、領収書を重ねてそれを1枚ずつめくる動画をGeminiに読み込ませると、経費精算に使えるような一覧表を自動作成してくれたり、複式簿記による会計仕訳を自動生成してくれるというものです。これが高精度でできてしまうと、AI-OCR対応の会計ソフトが要らなくなるかもしれません。AIを使いこなせない会計事務所は近い将来消滅してしまうのでは、と思いましたね。
生成AIの使い道は無限で、例えば自社の経営現況を詳しくプロンプト入力して、「5年後に年商10億円にするために必要な経営計画を、同業他社の傾向も踏まえて、マーケティング面、人事面、財務面を中心に立ててください」と質問すると、豊富な情報量を元に、精度の高い計画を立案してくれます。上場企業でも、自社でカスタマイズした生成AIの回答を元に新商品を開発したり、経営そのものを行っている会社があるくらいです。
ただあくまでも生成AIの提示するものは「提案」であり、それを元に思考し、決断し、行動するのは経営者自身です。ボスは社長であることに変わりない、ということさえ忘れなければ、生成AIはとても優秀なパートナー、アシスタントになってくれると思います。
生成AIは日進月歩でどんどん使い方も変わってくると思います。事業経営にもプライベートにもうまく活用して、人生を高めるものにしていきたいですね。
- < 前
- Page 1 / 34
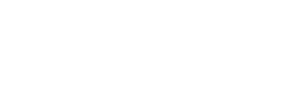

 RSS 2.0
RSS 2.0