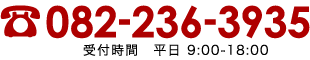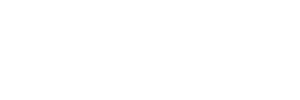ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
8月5日の株価暴落について
2024/09/02 13:19:10 株式投資
コメント (0)
8月5日に日経平均株価が暴落し、前日比△4,451円安の31,458円で取引を終え、ブラックマンデー超えの過去最大下げ幅になりました。日経平均はこの前から8月1日に△975円安、8月2日に△2,217円安と大幅下落が続いており(8月3・4日は土日で市場は休み)、8月2日時点でかなりヤバい雰囲気にはなっていました。
8月5日は私が持っていた三井住友銀行株もストップ安で張り付くなど、大型株も含めてありえないほどの下げに見舞われ、こんなことはトヨタ自動車が朝からストップ安に張り付いたリーマンショックの時以来の衝撃でした。しかし8月6日は大幅に上昇に転じて3,217円高の34,675円で終了、その後も上昇を続けて8月16日には終値が38,062円と、ほぼ7月末時点の暴落前の価格まで戻りました。
今回の下げは7月31日に日銀が突如利上げを発表したこと(事前予測では7月は利上げは見送られると見られていた)、それによる急激な円高の進行、そして円高に誘発されて日経平均が暴落しました。さらにアメリカ景気の先行き不安を示す指標が発表されたことが重なり、アメリカ投資家が円キャリートレード(金利の安い円で借金して、その円でドルを買って投資すること)を急激に巻き戻してアメリカの株価も暴落、アルゴリズムによる自動売買プログラムもその動きに拍車をかけ、全世界の市場が完全にパニック、最後は止まらない暴落の恐怖から投げ売りが連鎖してこんなひどいことになりました。
しかし、これは私の完全な後出しジャンケンですが、今回の暴落はすぐ終わるだろうと思っていました(←苦情は受け付けません笑)。理由は「暴落が長引くようなイベントは何も起こっていなかったから」です。端を発した日銀の利上げですが、政策金利を0.1%から0.25%に、たった0.15%上げただけです。しかも「今後市場が混乱するような利上げはしない」と後で火消しにまで走っています。実際のところアメリカとの金利差はまだまだ大きく、冷静になればある程度株価が下がれば織り込む程度のイベントでした。またアメリカで発表された指標も、アメリカ経済がハードランディングするほどの内容ではありませんでした。
最近は自動売買プログラムの影響で急激に株価が一方向に動きやすいのですが、「リーマン・ブラザーズの破綻が実体経済にどのくらいの規模・期間の悪影響を与えるかわからない」という実態を伴うダメージが起こったリーマンショックとは根底が異なるものでした。実際に今回ブラックマンデー超えの暴落でありながら、「○○ショック」のような名前がつくこともありませんでした。ただしこの暴落が、次の何らかの理由ある暴落の火種になる可能性はあります。注意しながら資産運用をして行きましょう。
8月5日は私が持っていた三井住友銀行株もストップ安で張り付くなど、大型株も含めてありえないほどの下げに見舞われ、こんなことはトヨタ自動車が朝からストップ安に張り付いたリーマンショックの時以来の衝撃でした。しかし8月6日は大幅に上昇に転じて3,217円高の34,675円で終了、その後も上昇を続けて8月16日には終値が38,062円と、ほぼ7月末時点の暴落前の価格まで戻りました。
今回の下げは7月31日に日銀が突如利上げを発表したこと(事前予測では7月は利上げは見送られると見られていた)、それによる急激な円高の進行、そして円高に誘発されて日経平均が暴落しました。さらにアメリカ景気の先行き不安を示す指標が発表されたことが重なり、アメリカ投資家が円キャリートレード(金利の安い円で借金して、その円でドルを買って投資すること)を急激に巻き戻してアメリカの株価も暴落、アルゴリズムによる自動売買プログラムもその動きに拍車をかけ、全世界の市場が完全にパニック、最後は止まらない暴落の恐怖から投げ売りが連鎖してこんなひどいことになりました。
しかし、これは私の完全な後出しジャンケンですが、今回の暴落はすぐ終わるだろうと思っていました(←苦情は受け付けません笑)。理由は「暴落が長引くようなイベントは何も起こっていなかったから」です。端を発した日銀の利上げですが、政策金利を0.1%から0.25%に、たった0.15%上げただけです。しかも「今後市場が混乱するような利上げはしない」と後で火消しにまで走っています。実際のところアメリカとの金利差はまだまだ大きく、冷静になればある程度株価が下がれば織り込む程度のイベントでした。またアメリカで発表された指標も、アメリカ経済がハードランディングするほどの内容ではありませんでした。
最近は自動売買プログラムの影響で急激に株価が一方向に動きやすいのですが、「リーマン・ブラザーズの破綻が実体経済にどのくらいの規模・期間の悪影響を与えるかわからない」という実態を伴うダメージが起こったリーマンショックとは根底が異なるものでした。実際に今回ブラックマンデー超えの暴落でありながら、「○○ショック」のような名前がつくこともありませんでした。ただしこの暴落が、次の何らかの理由ある暴落の火種になる可能性はあります。注意しながら資産運用をして行きましょう。
新NISAがスタート!さあ何に投資する?
2024/02/01 17:47:08 株式投資
コメント (0)
今年の1月から新NISAが始まり、この1ヶ月の間に日経平均も33,000円から一時37,000円まで駆け上がりました。元々日本株が上昇する要因はいくつかあったのですが(詳しくは令和5年7月号の沢辺通信に書いています。HPからも見れます!)、それに加えてこの新NISA資金流入を期待して欧米の機関資金も入ってきたこと(実際の新NISA資金はまだそこまで入っていない模様)、また景気が悪くなってきた中国への投資資金も日本に流れて来ているようです。
では、私達も乗り遅れないように新NISAを使って投資をして行きたいですが、何を買えばいいでしょうか?特に積立NISA用として人気があるのは、世界中の株式に分散投資している投資信託(オール・カントリー型。略して「オルカン」と言われている)です。個別株は何を買っていいかわからないし、経済成長の地域差はあっても世界全体では経済成長は続いていくでしょう!と思う方にはピッタリです。世界の経済は繋がっているので必ずしもリスク分散にならない部分はありますが、ドルコスト平均法を使って積み立てていくといいと思います(令和5年11月号の沢辺通信も参照して下さい)。それ以外では、特に経済成長が著しいインドの株式で運用している投資信託なども狙い目だと思います。
個別株を買いたい!という方もおられると思います。一般的にはJTやソフトバンクなど、配当利回りが5%前後ある大型株を推奨する記事等が多いですが、配当金以上に株価が下落しては意味がないので、絶対潰れない企業+(緩やかでもいいから)安定成長していて株価も比較的安定+それなりの配当利回り、が見込める銘柄を選びたいです。
その筆頭は、やはり令和5年11月号で取り上げたNTTですが、他にも今なら銀行株も狙い目だと思います。メガバンクは結構値動きが大きめなので、(もともと安値で放置されていた)地銀のほうがNISAには向いている気がします。広島銀行で現在配当利回り3.6%くらいですから、まずまずだと思います。
一昔前なら電力株も狙い目だったと思いますが、現在は原発にかかわるトラブル、コロナ禍での発電コストの上昇など、リスクも小さくない業種になってしまいました。ただコスト上昇は、電気代を値上げしちゃえば吸収できることが今回明らかになりました。成長性は少ないと思いますが、タイミングによってはNISA対象に考えるのもアリではないでしょうか。
今後の市場規模拡大が見込め、地政学リスクから日本国内への工場誘致も相次ぐ半導体関連株が現在株式市場では注目度ダントツですが、値動きがかなり荒く、配当利回りがあまり高くないのでNISAには不向きです。NISAで買った株式で損失が出ても損益通算できませんので、株価が大きく下落するとNISAのデメリットをもろに受けてしまう可能性があります。
なお、これらの内容はあくまで個人的見解を述べているだけであり、売買を指示、推奨しているわけでは一切ありません。投資は自己責任でお願いします!
では、私達も乗り遅れないように新NISAを使って投資をして行きたいですが、何を買えばいいでしょうか?特に積立NISA用として人気があるのは、世界中の株式に分散投資している投資信託(オール・カントリー型。略して「オルカン」と言われている)です。個別株は何を買っていいかわからないし、経済成長の地域差はあっても世界全体では経済成長は続いていくでしょう!と思う方にはピッタリです。世界の経済は繋がっているので必ずしもリスク分散にならない部分はありますが、ドルコスト平均法を使って積み立てていくといいと思います(令和5年11月号の沢辺通信も参照して下さい)。それ以外では、特に経済成長が著しいインドの株式で運用している投資信託なども狙い目だと思います。
個別株を買いたい!という方もおられると思います。一般的にはJTやソフトバンクなど、配当利回りが5%前後ある大型株を推奨する記事等が多いですが、配当金以上に株価が下落しては意味がないので、絶対潰れない企業+(緩やかでもいいから)安定成長していて株価も比較的安定+それなりの配当利回り、が見込める銘柄を選びたいです。
その筆頭は、やはり令和5年11月号で取り上げたNTTですが、他にも今なら銀行株も狙い目だと思います。メガバンクは結構値動きが大きめなので、(もともと安値で放置されていた)地銀のほうがNISAには向いている気がします。広島銀行で現在配当利回り3.6%くらいですから、まずまずだと思います。
一昔前なら電力株も狙い目だったと思いますが、現在は原発にかかわるトラブル、コロナ禍での発電コストの上昇など、リスクも小さくない業種になってしまいました。ただコスト上昇は、電気代を値上げしちゃえば吸収できることが今回明らかになりました。成長性は少ないと思いますが、タイミングによってはNISA対象に考えるのもアリではないでしょうか。
今後の市場規模拡大が見込め、地政学リスクから日本国内への工場誘致も相次ぐ半導体関連株が現在株式市場では注目度ダントツですが、値動きがかなり荒く、配当利回りがあまり高くないのでNISAには不向きです。NISAで買った株式で損失が出ても損益通算できませんので、株価が大きく下落するとNISAのデメリットをもろに受けてしまう可能性があります。
なお、これらの内容はあくまで個人的見解を述べているだけであり、売買を指示、推奨しているわけでは一切ありません。投資は自己責任でお願いします!
新NISAも始まるので、投資について考える
2023/11/01 16:53:18 株式投資
コメント (0)
以前も取り上げましたが、令和6年1月よりNISA制度の改正があります。投資枠が2~3倍程度、非課税期間が無期限になり、特に長期投資に有利になりました。かなり税制上の優遇をするから、老後資金は自分で運用してくれという国の意図がはっきり見えます。
最近では株式でも配当利回りが5%を超えるような銘柄も散見されますので、これらの配当を無税で受け取り、将来的に値上がりした元本も無税で換金できれば文句なし!ですが、長期投資で株式や投資信託を購入するからには値下がりリスクも当然発生します。その長期投資リスクをなるべく軽減するためによく言われるのが「分散投資」です。
分散投資だ!ということで世界各国の投資信託等を少しづつ購入する方もおられますが、これはおすすめできません。世界経済は繋がっており、どこかで暴落が起きれば他の場所でも影響が波及して暴落するのが常です。「地域分散」の考え方では、すべてが同時にコケるので結局リスクヘッジにならないのです。
ですので、分散を考えるなら「時間分散」、つまり購入する日時を分散してリスクを軽減するのが正しいです。「ドルコスト平均法」はまさにこの考え方で、暴落があった時期には同じ資金でより多くの株式等を取得できるので、平均取得単価を下げることに繋がります。
個別の株式に目を向けますと、新NISAを意識して、安定した個人株主を増やしたいという動きが増えています。例えばNTTは今年7月に1株→25株へ株式分割を行い、1単元(=100株)を18,000円前後で買えるようにしました。この金額でしたら、毎月予算に合わせて数万円ずつ積み立て感覚で株式の買い増しができます。NTTは将来的に日本政府が株式を売却していく方向で議論されていますが、国外事業展開をしやすくするため、という噂もあります。そうなると将来性も高く、安定した成長と配当、かつ絶対潰れないであろう企業ということでNISAには最適な銘柄だと思います(購入は自己責任でお願いします!)。
最近では株式でも配当利回りが5%を超えるような銘柄も散見されますので、これらの配当を無税で受け取り、将来的に値上がりした元本も無税で換金できれば文句なし!ですが、長期投資で株式や投資信託を購入するからには値下がりリスクも当然発生します。その長期投資リスクをなるべく軽減するためによく言われるのが「分散投資」です。
分散投資だ!ということで世界各国の投資信託等を少しづつ購入する方もおられますが、これはおすすめできません。世界経済は繋がっており、どこかで暴落が起きれば他の場所でも影響が波及して暴落するのが常です。「地域分散」の考え方では、すべてが同時にコケるので結局リスクヘッジにならないのです。
ですので、分散を考えるなら「時間分散」、つまり購入する日時を分散してリスクを軽減するのが正しいです。「ドルコスト平均法」はまさにこの考え方で、暴落があった時期には同じ資金でより多くの株式等を取得できるので、平均取得単価を下げることに繋がります。
個別の株式に目を向けますと、新NISAを意識して、安定した個人株主を増やしたいという動きが増えています。例えばNTTは今年7月に1株→25株へ株式分割を行い、1単元(=100株)を18,000円前後で買えるようにしました。この金額でしたら、毎月予算に合わせて数万円ずつ積み立て感覚で株式の買い増しができます。NTTは将来的に日本政府が株式を売却していく方向で議論されていますが、国外事業展開をしやすくするため、という噂もあります。そうなると将来性も高く、安定した成長と配当、かつ絶対潰れないであろう企業ということでNISAには最適な銘柄だと思います(購入は自己責任でお願いします!)。
日経平均はバブル超えの4万円に届くか!?
2023/07/03 15:02:18 株式投資
コメント (0)
日経平均株価が強いです。7/3現在で33,700円前後で推移していますが、4月時点では28,000円前後でした。この3ヶ月間一本調子で5,000円以上上がり続け、現在に至ります。この間アメリカが下がっても日本株だけは独歩高の強さで、最終的にはバブル高値(1989年末の38,915円)を超えて4万円に到達するのでは?という声も出始めております。
今回ここまで日経平均が上がっている理由ですが、実は結構わかりやすい材料が複数重なっており、この上昇はまだまだ続く可能性があります。一つずつ取り上げてみたいと思います。
(1)半導体工場等の日本回帰
半導体は「令和の米」と言われるほどあらゆる製品・武器を作るのに欠かせないもので、アメリカはその半導体の先端技術品サプライチェーンから中国を分断する動きを露骨に行っています。その一端として台湾の「半導体製造の巨人」TSMCの工場を、台湾有事に備えてアメリカや日本(熊本)に建設を始めています。また日本企業も北海道などに政府の援助を受けて先端半導体工場を建設するなど、今や物価・賃金安、円安で中国よりもコストを安く抑えられて政治的リスクも低い日本国内への工場誘致が活発化しており、これが日本経済活発化の期待を呼んでいます。
(2)バフェットの日本株買い増し
伝説の投資家ウォーレン・バフェット氏が3年前から三菱商事などの商社株を買い増す意向を表明し、今も買い増しを続けております。商社株は過去にないほどの上昇を続けており、あのバフェットが日本株をこんなに買い増しているのだから、日本株は間違いない!とばかりに国外の資金が日本株に集中しています。また中国や韓国の経済の将来性がかなり危ぶまれており、特に中国は不動産バブル崩壊秒読みとも言われていますので、アジア方面への投資資金が中国から日本に相当流れているようです。
(3)日本証券取引所の「異例の」改善要請
日本証券取引所がPBR1倍割れの企業に対して、「もっと資本効率や収益性の改善をしなさい」と異例の要請を行っていることも話題になっています。PBR1倍割れというのは、例えばその企業の純資産が3,000億円あるのに、株価の時価総額(=株価×株数)が1,500億円しかない(この場合PBR=0.5となる)状態で、株主からすれば、すぐに会社を解散して資産を分配してくれたほうが株式の価値が2倍になる計算です。「そんな状態での経営って、ダメでしょ」「もっと株価が上がる努力をしなさいよ」と日本証券取引所がお叱りを入れたわけです。これを受けて、例えば銀行などは今期大幅な増配を発表しており、1株あたり配当金を、三菱東京UFJが32円→41円、広島銀行が27円→36円など、投資冥利が上がって来ています。
今回ここまで日経平均が上がっている理由ですが、実は結構わかりやすい材料が複数重なっており、この上昇はまだまだ続く可能性があります。一つずつ取り上げてみたいと思います。
(1)半導体工場等の日本回帰
半導体は「令和の米」と言われるほどあらゆる製品・武器を作るのに欠かせないもので、アメリカはその半導体の先端技術品サプライチェーンから中国を分断する動きを露骨に行っています。その一端として台湾の「半導体製造の巨人」TSMCの工場を、台湾有事に備えてアメリカや日本(熊本)に建設を始めています。また日本企業も北海道などに政府の援助を受けて先端半導体工場を建設するなど、今や物価・賃金安、円安で中国よりもコストを安く抑えられて政治的リスクも低い日本国内への工場誘致が活発化しており、これが日本経済活発化の期待を呼んでいます。
(2)バフェットの日本株買い増し
伝説の投資家ウォーレン・バフェット氏が3年前から三菱商事などの商社株を買い増す意向を表明し、今も買い増しを続けております。商社株は過去にないほどの上昇を続けており、あのバフェットが日本株をこんなに買い増しているのだから、日本株は間違いない!とばかりに国外の資金が日本株に集中しています。また中国や韓国の経済の将来性がかなり危ぶまれており、特に中国は不動産バブル崩壊秒読みとも言われていますので、アジア方面への投資資金が中国から日本に相当流れているようです。
(3)日本証券取引所の「異例の」改善要請
日本証券取引所がPBR1倍割れの企業に対して、「もっと資本効率や収益性の改善をしなさい」と異例の要請を行っていることも話題になっています。PBR1倍割れというのは、例えばその企業の純資産が3,000億円あるのに、株価の時価総額(=株価×株数)が1,500億円しかない(この場合PBR=0.5となる)状態で、株主からすれば、すぐに会社を解散して資産を分配してくれたほうが株式の価値が2倍になる計算です。「そんな状態での経営って、ダメでしょ」「もっと株価が上がる努力をしなさいよ」と日本証券取引所がお叱りを入れたわけです。これを受けて、例えば銀行などは今期大幅な増配を発表しており、1株あたり配当金を、三菱東京UFJが32円→41円、広島銀行が27円→36円など、投資冥利が上がって来ています。
損したのに課税される?仮想通貨の「総平均法」
2021/06/29 15:13:12 株式投資
コメント (0)
世界各国でコロナによる経済腰折れを防ぐべく大規模な財政出動がなされた結果、その資金の一部は株式市場のみならず、金(きん)などの資産や、果ては高級時計や絵画などにも投資・投機資金として流れ、高騰の一途をたどって来ました。最近ではコロナ後の景気V字回復は既定路線で、その後のインフレ懸念で利上げが早期に行われるという警戒感が市場の話題の中心となりつつある状況です。
ところで、一時はほぼ話題に上がらなくなった仮想通貨(=暗号資産)も昨年12月頃から大幅上昇しており、例えばビットコインは昨年秋100万円→今年4月高値700万円→6月400万円、と波乱の動きになっています。こうなると3年前同様に仮想通貨の利益を確定申告する方が多数出てくると思うのですが、当時と比べて確定申告時の計算方法も整備が進んでおり、国税庁もかなり詳細なQ&Aや計算用のエクセルシートまでHP上で発表しております。
基本的な計算方法が3年前と変わった訳ではないのですが、1点気になったのは「評価方法の届出がない場合は、総平均法で計算する」(令和1年度より)という部分です。
計算方法には移動平均法と総平均法があり、移動平均法は売買の都度平均単価を計算し直していく方法で、総平均法はその1年間で買った金額と数量を全部足し算して、年末に初めて平均単価を出す方法です。通常トレードする場合はその都度利益が出たか知りたいので、移動平均法の計算を(自然に)行っているのですが、怖いのは移動平均法だと損してるのに総平均法だと利益が出てる計算になる可能性があることです。
例えば①500万円で1BTC買い、②450万円で1BTC売り、③300万円で1BTC買い(保有中)の場合、移動平均法では①と②だけを考えるので50万円の損になります。ところが総平均法だと(①+③)÷2の400万円が平均単価となるので、逆に50万円の利益になります。
もちろん逆のケースも起こりうるのですが、いずれにせよ総平均法は売買感覚に合わないので、仮想通貨の申告をされる場合は移動平均法の届出を合わせて出されることをおすすめします。確定申告書と同時に、翌年3/15までに提出すればOKです。
ところで、一時はほぼ話題に上がらなくなった仮想通貨(=暗号資産)も昨年12月頃から大幅上昇しており、例えばビットコインは昨年秋100万円→今年4月高値700万円→6月400万円、と波乱の動きになっています。こうなると3年前同様に仮想通貨の利益を確定申告する方が多数出てくると思うのですが、当時と比べて確定申告時の計算方法も整備が進んでおり、国税庁もかなり詳細なQ&Aや計算用のエクセルシートまでHP上で発表しております。
基本的な計算方法が3年前と変わった訳ではないのですが、1点気になったのは「評価方法の届出がない場合は、総平均法で計算する」(令和1年度より)という部分です。
計算方法には移動平均法と総平均法があり、移動平均法は売買の都度平均単価を計算し直していく方法で、総平均法はその1年間で買った金額と数量を全部足し算して、年末に初めて平均単価を出す方法です。通常トレードする場合はその都度利益が出たか知りたいので、移動平均法の計算を(自然に)行っているのですが、怖いのは移動平均法だと損してるのに総平均法だと利益が出てる計算になる可能性があることです。
例えば①500万円で1BTC買い、②450万円で1BTC売り、③300万円で1BTC買い(保有中)の場合、移動平均法では①と②だけを考えるので50万円の損になります。ところが総平均法だと(①+③)÷2の400万円が平均単価となるので、逆に50万円の利益になります。
もちろん逆のケースも起こりうるのですが、いずれにせよ総平均法は売買感覚に合わないので、仮想通貨の申告をされる場合は移動平均法の届出を合わせて出されることをおすすめします。確定申告書と同時に、翌年3/15までに提出すればOKです。
- < 前
- Page 1 / 4
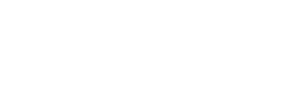

 RSS 2.0
RSS 2.0