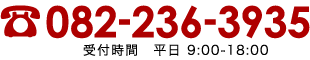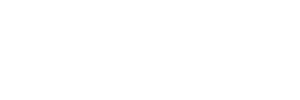ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
インボイス開始に向けての準備
2023/09/01 15:14:21 経理事務
コメント (0)
インボイス制度が本当に10月から始まってしまいます。登録申請や請求書・領収書への番号記載以外にも経理事務を変更しないといけない点がいくつかあります(引き続き消費税の免税事業者である方には必要ありません)。
まず、10月以降にクレジットカードで支払った経費は、都度領収書をもらって保管する必要があります。今までは原則1ヶ月ごとの利用明細書と帳簿記載のみで消費税の仕入税額控除が認められていましたが、これがしれっと廃止されました。税務調査が来た時にカード払いの経費の領収書がないと、原則消費税が否認されて追徴税額を納めないといけなくなるので、必ず保管をお願いします。
なお3万円未満のJR料金や自販機での商品購入に限り保管義務が免除されます。またETCは、ウェブ上の「ETC利用照会サービス」で交付される明細を保管すれば大丈夫です。
また自社で会計入力をされる場合は、経費の都度請求書・領収書にインボイス番号があるかどうかを確認して消費税入力をしていただく必要があります。例えば弥生会計の場合、番号があるものは「適格」、ないものは「区分記載80%」を選択します。手書きの振替伝票等を作成される場合は、番号のない経費は「番号なし」などと摘要に記載していただき、後で区別できるようにしていただければと思います。その他ご不明な点がありましたら、各担当者にお尋ねください。
まず、10月以降にクレジットカードで支払った経費は、都度領収書をもらって保管する必要があります。今までは原則1ヶ月ごとの利用明細書と帳簿記載のみで消費税の仕入税額控除が認められていましたが、これがしれっと廃止されました。税務調査が来た時にカード払いの経費の領収書がないと、原則消費税が否認されて追徴税額を納めないといけなくなるので、必ず保管をお願いします。
なお3万円未満のJR料金や自販機での商品購入に限り保管義務が免除されます。またETCは、ウェブ上の「ETC利用照会サービス」で交付される明細を保管すれば大丈夫です。
また自社で会計入力をされる場合は、経費の都度請求書・領収書にインボイス番号があるかどうかを確認して消費税入力をしていただく必要があります。例えば弥生会計の場合、番号があるものは「適格」、ないものは「区分記載80%」を選択します。手書きの振替伝票等を作成される場合は、番号のない経費は「番号なし」などと摘要に記載していただき、後で区別できるようにしていただければと思います。その他ご不明な点がありましたら、各担当者にお尋ねください。
最低賃金引き上げ
2023/09/01 15:13:20 経済一般
コメント (0)
今年10月から最低賃金が引き上げられます。広島県では930円→970円となり、全国平均は1,002円です。実質的にも時給1,000円は最低ラインとなります。
岸田総理は、2030年代半ばまでに全国平均を1,500円まで引き上げたい、と言っています。私が大学生の時(30年くらい前)に当時のほぼ最低時給650円でアルバイトしていた記憶がありますので、この30年間で最低賃金が1.5倍くらいになっています。今度は10数年でさらに1.5倍にするわけですね。
毎年3%ずつ賃金が上がれば達成する金額なので実現不可能ではないと思いますが、最近は働き方改革などで日本人の労働時間はかなり減っています。その上これだけ賃金が上がると、コスト高、人材不足で企業経営が成り立たなくなり、国際競争力も低下する恐れがあります。そうならないためには、「ムダなく成果を上げる働き方」を今以上に追求していかなければなりません。ただでさえ日本の働き方は非効率だと国外からバカにされるわけですから、「ろくに働いていない高給取り」が日本からいなくなるような政策と企業風土がより重要になっていきます。
また賃金が1.5倍になるということは、それだけインフレにもなるということです。資産運用の重要性等もより高くなっていきます。
岸田総理は、2030年代半ばまでに全国平均を1,500円まで引き上げたい、と言っています。私が大学生の時(30年くらい前)に当時のほぼ最低時給650円でアルバイトしていた記憶がありますので、この30年間で最低賃金が1.5倍くらいになっています。今度は10数年でさらに1.5倍にするわけですね。
毎年3%ずつ賃金が上がれば達成する金額なので実現不可能ではないと思いますが、最近は働き方改革などで日本人の労働時間はかなり減っています。その上これだけ賃金が上がると、コスト高、人材不足で企業経営が成り立たなくなり、国際競争力も低下する恐れがあります。そうならないためには、「ムダなく成果を上げる働き方」を今以上に追求していかなければなりません。ただでさえ日本の働き方は非効率だと国外からバカにされるわけですから、「ろくに働いていない高給取り」が日本からいなくなるような政策と企業風土がより重要になっていきます。
また賃金が1.5倍になるということは、それだけインフレにもなるということです。資産運用の重要性等もより高くなっていきます。
中国の凋落と日本の特需
2023/08/01 15:35:11 経済一般
コメント (0)
中国は人口減少と経済の落ち込みで今後かなり苦しくなるのではないか、と言われています。長年続いた一人っ子政策の弊害で、少子高齢化に伴う労働人口の減少に歯止めがかからないのです。それなのに中国はマンションを建設し続け、今や人口(14億)の2~3倍が住める件数があるそうです。
その上投機により膨らんだ不動産バブル対策として、3年前から不動産開発企業への銀行融資規制を始めたため次々とデフォルト(債務不履行)が発生、最大手の中国恒大集団一社だけでも47兆円負債を抱えて債務超過に陥るなど、連鎖倒産すればその余波は中国国内にとどまらない可能性もあります。極端に言えば、もともと中国の景気刺激策は住む人のいないマンション開発で成り立っていたというわけです。
その上「令和のコメ」と言われている半導体分野でもアメリカの輸出規制により、特に最先端技術の半導体は中国国内での製造が難しくなっていきます。アメリカは中国なしで最先端半導体が製造できるよう、同盟国で政治、治安とも安定しており、人件費も安い日本での半導体工場建設を促しています。これは日本にとって最後のチャンスかもしれない特需です。戦後日本が朝鮮戦争の特需で復活したように、米中新冷戦下での特需をしっかりと享受して、失われた30年を取り戻していかないといけません。
その上投機により膨らんだ不動産バブル対策として、3年前から不動産開発企業への銀行融資規制を始めたため次々とデフォルト(債務不履行)が発生、最大手の中国恒大集団一社だけでも47兆円負債を抱えて債務超過に陥るなど、連鎖倒産すればその余波は中国国内にとどまらない可能性もあります。極端に言えば、もともと中国の景気刺激策は住む人のいないマンション開発で成り立っていたというわけです。
その上「令和のコメ」と言われている半導体分野でもアメリカの輸出規制により、特に最先端技術の半導体は中国国内での製造が難しくなっていきます。アメリカは中国なしで最先端半導体が製造できるよう、同盟国で政治、治安とも安定しており、人件費も安い日本での半導体工場建設を促しています。これは日本にとって最後のチャンスかもしれない特需です。戦後日本が朝鮮戦争の特需で復活したように、米中新冷戦下での特需をしっかりと享受して、失われた30年を取り戻していかないといけません。
ビッグモーター問題
2023/08/01 15:33:37 経済一般
コメント (0)
ビッグモーター問題が大きくなっています。二代目オーナー社長による典型的なパワハラ経営といった感じですが、こういった企業は昔から日本にたくさんあるのでしょうね。昭和の時代から何も変わらない、根性論の経営ですね。
岩国市で創業したビッグモーターは特に二代目になってから出店ペースを急激に増やし、現在300店舗位あるようですが、消費人口が減少し続けている日本ではニーズ以上に拡大させすぎてしまったのでしょうね。ニーズがないから売上・利益が伸び悩む、でも二代目社長はお父さんである創業社長に認められたい、そんなプレッシャーからパワハラ経営に傾いていったのかもしれません。まあ、そもそもの人間性がそうでなければ、プレッシャーだけでパワハラ体質に変わるとは思えませんが・・。
1日1,000件のLINEとか、店舗視察でその場で降格言い渡しとか、労働基準法の存在を知らないような信じられない内容です。LINEのスクショや録音を労働基準監督署に持ち込まれればアウトだと思うのですが、それすらもみ消してきたのですかね。威圧だけで経営するならヤクザと一緒です。お客様や従業員と真摯に向かい合った経営をしたいものです。
岩国市で創業したビッグモーターは特に二代目になってから出店ペースを急激に増やし、現在300店舗位あるようですが、消費人口が減少し続けている日本ではニーズ以上に拡大させすぎてしまったのでしょうね。ニーズがないから売上・利益が伸び悩む、でも二代目社長はお父さんである創業社長に認められたい、そんなプレッシャーからパワハラ経営に傾いていったのかもしれません。まあ、そもそもの人間性がそうでなければ、プレッシャーだけでパワハラ体質に変わるとは思えませんが・・。
1日1,000件のLINEとか、店舗視察でその場で降格言い渡しとか、労働基準法の存在を知らないような信じられない内容です。LINEのスクショや録音を労働基準監督署に持ち込まれればアウトだと思うのですが、それすらもみ消してきたのですかね。威圧だけで経営するならヤクザと一緒です。お客様や従業員と真摯に向かい合った経営をしたいものです。
日経平均はバブル超えの4万円に届くか!?
2023/07/03 15:02:18 株式投資
コメント (0)
日経平均株価が強いです。7/3現在で33,700円前後で推移していますが、4月時点では28,000円前後でした。この3ヶ月間一本調子で5,000円以上上がり続け、現在に至ります。この間アメリカが下がっても日本株だけは独歩高の強さで、最終的にはバブル高値(1989年末の38,915円)を超えて4万円に到達するのでは?という声も出始めております。
今回ここまで日経平均が上がっている理由ですが、実は結構わかりやすい材料が複数重なっており、この上昇はまだまだ続く可能性があります。一つずつ取り上げてみたいと思います。
(1)半導体工場等の日本回帰
半導体は「令和の米」と言われるほどあらゆる製品・武器を作るのに欠かせないもので、アメリカはその半導体の先端技術品サプライチェーンから中国を分断する動きを露骨に行っています。その一端として台湾の「半導体製造の巨人」TSMCの工場を、台湾有事に備えてアメリカや日本(熊本)に建設を始めています。また日本企業も北海道などに政府の援助を受けて先端半導体工場を建設するなど、今や物価・賃金安、円安で中国よりもコストを安く抑えられて政治的リスクも低い日本国内への工場誘致が活発化しており、これが日本経済活発化の期待を呼んでいます。
(2)バフェットの日本株買い増し
伝説の投資家ウォーレン・バフェット氏が3年前から三菱商事などの商社株を買い増す意向を表明し、今も買い増しを続けております。商社株は過去にないほどの上昇を続けており、あのバフェットが日本株をこんなに買い増しているのだから、日本株は間違いない!とばかりに国外の資金が日本株に集中しています。また中国や韓国の経済の将来性がかなり危ぶまれており、特に中国は不動産バブル崩壊秒読みとも言われていますので、アジア方面への投資資金が中国から日本に相当流れているようです。
(3)日本証券取引所の「異例の」改善要請
日本証券取引所がPBR1倍割れの企業に対して、「もっと資本効率や収益性の改善をしなさい」と異例の要請を行っていることも話題になっています。PBR1倍割れというのは、例えばその企業の純資産が3,000億円あるのに、株価の時価総額(=株価×株数)が1,500億円しかない(この場合PBR=0.5となる)状態で、株主からすれば、すぐに会社を解散して資産を分配してくれたほうが株式の価値が2倍になる計算です。「そんな状態での経営って、ダメでしょ」「もっと株価が上がる努力をしなさいよ」と日本証券取引所がお叱りを入れたわけです。これを受けて、例えば銀行などは今期大幅な増配を発表しており、1株あたり配当金を、三菱東京UFJが32円→41円、広島銀行が27円→36円など、投資冥利が上がって来ています。
今回ここまで日経平均が上がっている理由ですが、実は結構わかりやすい材料が複数重なっており、この上昇はまだまだ続く可能性があります。一つずつ取り上げてみたいと思います。
(1)半導体工場等の日本回帰
半導体は「令和の米」と言われるほどあらゆる製品・武器を作るのに欠かせないもので、アメリカはその半導体の先端技術品サプライチェーンから中国を分断する動きを露骨に行っています。その一端として台湾の「半導体製造の巨人」TSMCの工場を、台湾有事に備えてアメリカや日本(熊本)に建設を始めています。また日本企業も北海道などに政府の援助を受けて先端半導体工場を建設するなど、今や物価・賃金安、円安で中国よりもコストを安く抑えられて政治的リスクも低い日本国内への工場誘致が活発化しており、これが日本経済活発化の期待を呼んでいます。
(2)バフェットの日本株買い増し
伝説の投資家ウォーレン・バフェット氏が3年前から三菱商事などの商社株を買い増す意向を表明し、今も買い増しを続けております。商社株は過去にないほどの上昇を続けており、あのバフェットが日本株をこんなに買い増しているのだから、日本株は間違いない!とばかりに国外の資金が日本株に集中しています。また中国や韓国の経済の将来性がかなり危ぶまれており、特に中国は不動産バブル崩壊秒読みとも言われていますので、アジア方面への投資資金が中国から日本に相当流れているようです。
(3)日本証券取引所の「異例の」改善要請
日本証券取引所がPBR1倍割れの企業に対して、「もっと資本効率や収益性の改善をしなさい」と異例の要請を行っていることも話題になっています。PBR1倍割れというのは、例えばその企業の純資産が3,000億円あるのに、株価の時価総額(=株価×株数)が1,500億円しかない(この場合PBR=0.5となる)状態で、株主からすれば、すぐに会社を解散して資産を分配してくれたほうが株式の価値が2倍になる計算です。「そんな状態での経営って、ダメでしょ」「もっと株価が上がる努力をしなさいよ」と日本証券取引所がお叱りを入れたわけです。これを受けて、例えば銀行などは今期大幅な増配を発表しており、1株あたり配当金を、三菱東京UFJが32円→41円、広島銀行が27円→36円など、投資冥利が上がって来ています。
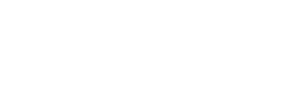

 RSS 2.0
RSS 2.0