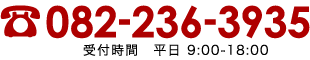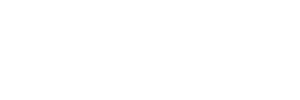ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
シャープが中小企業に!? 「1億円に減資」とは
2015/05/31 15:12:52 経済一般
コメント (0)
シャープという日本を代表するグローバル企業があります。一時は「世界の亀山モデル」と自負する液晶TVなどの液晶関連製品で好調でしたが、ここ数年は液晶自体の差別化が難しくなってきており、液晶関連に設備投資を集中しすぎた反動もあり、ここ3年で9,000億円の連結赤字を出すなど業績が急激に悪化しております。
そのシャープが新中期計画の一環として5/11に発表した(正確にはリークされた)のが、「1億円に減資」して「中小企業」となり、「中小企業の税制上の優遇措置を受けながら経営を立て直す」というものでした。
「えっ、あのシャープが中小企業って・・!?」という強烈なインパクトの発表でした。正直、「そんなのありなの?売上約3兆円、従業員5万人で中小企業??」と思いました。でも、中小企業の定義はいくつかあるものの、法人税法上の中小企業の判定は「資本金が1億円以下か否か」だけなのです。売上高も従業員数も関係なし。
「確かに合法だけど、そこまでやるか・・」と思っておりましたら、翌12日に経済産業省の「企業再生としては違和感がある」などの指摘を受けて、13日には「やっぱり資本金は5億円にします(現在は約1,200億円)」と発表しました。現場の混乱や、政界とのパイプの薄さが露呈されてしまいました。 結局、14日の決算発表では2,223億円の最終赤字を出し、単体決算ではとうとう債務超過になってしまいました。
そもそも、「減資」と経営再建は関連があるのでしょうか?シャープが行う予定の減資は、資本金を過去の利益剰余金のマイナスと相殺するというもので、乱暴に言いますと「資本金/利益剰余金」という仕訳を帳簿上で切るだけです。実質的には何も変わりません。既存株主にも、特に有利にも不利にも働きません。
既出の「優遇措置を受ける」とか、また累積損失が消えることによって「将来、配当を出しやすくする」などとニュースでは出ていましたが、正直、存続すら危うい企業が将来株主に出す配当のことなど優先して考えている場合ではありません。表に出ていない本当のねらいがあるはずなのです。
有力な考えとしては、将来増資をして資金調達をするための布石、ということです。「増資のための減資」です。今回の減資では株主には有利不利はないと書きましたが、将来多額の増資を行えば、一株ごとの価値は大きく下がります(要するに株価が下がります)。今は、インターネット上でいくらでも情報があふれているように見えますが、本当に大切な情報は、やはりどこか一部で握られていると考えるべきだと思います。
そのシャープが新中期計画の一環として5/11に発表した(正確にはリークされた)のが、「1億円に減資」して「中小企業」となり、「中小企業の税制上の優遇措置を受けながら経営を立て直す」というものでした。
「えっ、あのシャープが中小企業って・・!?」という強烈なインパクトの発表でした。正直、「そんなのありなの?売上約3兆円、従業員5万人で中小企業??」と思いました。でも、中小企業の定義はいくつかあるものの、法人税法上の中小企業の判定は「資本金が1億円以下か否か」だけなのです。売上高も従業員数も関係なし。
「確かに合法だけど、そこまでやるか・・」と思っておりましたら、翌12日に経済産業省の「企業再生としては違和感がある」などの指摘を受けて、13日には「やっぱり資本金は5億円にします(現在は約1,200億円)」と発表しました。現場の混乱や、政界とのパイプの薄さが露呈されてしまいました。 結局、14日の決算発表では2,223億円の最終赤字を出し、単体決算ではとうとう債務超過になってしまいました。
そもそも、「減資」と経営再建は関連があるのでしょうか?シャープが行う予定の減資は、資本金を過去の利益剰余金のマイナスと相殺するというもので、乱暴に言いますと「資本金/利益剰余金」という仕訳を帳簿上で切るだけです。実質的には何も変わりません。既存株主にも、特に有利にも不利にも働きません。
既出の「優遇措置を受ける」とか、また累積損失が消えることによって「将来、配当を出しやすくする」などとニュースでは出ていましたが、正直、存続すら危うい企業が将来株主に出す配当のことなど優先して考えている場合ではありません。表に出ていない本当のねらいがあるはずなのです。
有力な考えとしては、将来増資をして資金調達をするための布石、ということです。「増資のための減資」です。今回の減資では株主には有利不利はないと書きましたが、将来多額の増資を行えば、一株ごとの価値は大きく下がります(要するに株価が下がります)。今は、インターネット上でいくらでも情報があふれているように見えますが、本当に大切な情報は、やはりどこか一部で握られていると考えるべきだと思います。
女性の社会進出を阻む、103万円の壁と130万円の壁
2015/05/01 13:06:16 節税
コメント (0)
奥様がパートで働く、などの場合によく言われる「(年収)103万円の壁」。これを超えると扶養から外れたり、税金(所得税、住民税)が増えたりするらしい・・、と漠然とはわかっていても、意外と正確な仕組みはわかっていない場合があります。今回はこれを整理してみようと思います。
※以下、「年収」はすべて給与である前提とします。
まず、「扶養」には2種類あり、壁となる限度額が異なります。(1)税金の扶養から外れるのが年収103万円、(2)健康保険の扶養から外れるのが130万円、になります。この2つの違いがごっちゃにならないようにしなければなりません。
そして第一の壁、奥様の年収が103万円を超えたとき、何が起こるか。まず奥様本人の税金が発生しますが、これはわずかです。あまり気にする必要がありません。問題は、ご主人の「配偶者控除(38万円)」が外れることです。控除額が38万円ということは、ご主人の税率が33%だとすると、38万円×33%=125,400円の増税になります。実際には「配偶者特別控除」があるため、壁を1円でも上回った瞬間すぐに12万円が増税になるわけではありませんが、奥様が103万円を少し超える程度の年収だと、ご主人の税金が増え、かえってご夫婦の合算の手取り金額が減ってしまうという逆転現象が起こる可能性があります。また、ご主人の会社の社内規定によって、配偶者控除が外れると「家族手当」の支給が減額される、というようなケースもありますので注意が必要です。
次に第二の壁、奥様の年収が130万円を超えたとき、何が起こるか。奥様が健康保険の扶養から外れます。つまり、奥様が別途自分で健康保険に加入しないといけなくなります。そうなると社会保険料の負担が一気に大きくなります。特にご主人が政府管掌社会保険(いわゆる社保)に加入していた場合は、奥様は国民年金第3号被保険者として、年金の支払いが免除されているような扱いになっていましたが、これも自分で負担しないといけなくなったりします。ですので、奥様の年収が140万円位ですと、ほぼ確実に年収130万円弱の場合より夫婦の合算の手取りが減ります。10万円分以上のただ働き・・ということになってしまいます。一生懸命仕事したのに、かえって手取りは減り、子どもの保育園の保育料も上がった・・なんてことは絶対に避けたいですよね。
では、どうすればいいのか。方法は2つです。1つ目は、税金の負担と社会保険料の負担の増加を埋めるくらい、奥様が稼ぐことです。目安としては年収160~170万円以上です。ただそうなると、子どもさんが小さくて正社員としては働けない方には厳しい金額です。
となると、第2の方法、奥様の年収を103万円以下に抑える、という方法を取らざるを得なくなります。ひと月の収入を103万円÷12月=85,000円程度に抑える、年末近くなると103万円を超えないように勤務時間を調整する・・・。
この動きこそが、まさに女性の社会進出を阻む大きな壁となっているわけです。
※以下、「年収」はすべて給与である前提とします。
まず、「扶養」には2種類あり、壁となる限度額が異なります。(1)税金の扶養から外れるのが年収103万円、(2)健康保険の扶養から外れるのが130万円、になります。この2つの違いがごっちゃにならないようにしなければなりません。
そして第一の壁、奥様の年収が103万円を超えたとき、何が起こるか。まず奥様本人の税金が発生しますが、これはわずかです。あまり気にする必要がありません。問題は、ご主人の「配偶者控除(38万円)」が外れることです。控除額が38万円ということは、ご主人の税率が33%だとすると、38万円×33%=125,400円の増税になります。実際には「配偶者特別控除」があるため、壁を1円でも上回った瞬間すぐに12万円が増税になるわけではありませんが、奥様が103万円を少し超える程度の年収だと、ご主人の税金が増え、かえってご夫婦の合算の手取り金額が減ってしまうという逆転現象が起こる可能性があります。また、ご主人の会社の社内規定によって、配偶者控除が外れると「家族手当」の支給が減額される、というようなケースもありますので注意が必要です。
次に第二の壁、奥様の年収が130万円を超えたとき、何が起こるか。奥様が健康保険の扶養から外れます。つまり、奥様が別途自分で健康保険に加入しないといけなくなります。そうなると社会保険料の負担が一気に大きくなります。特にご主人が政府管掌社会保険(いわゆる社保)に加入していた場合は、奥様は国民年金第3号被保険者として、年金の支払いが免除されているような扱いになっていましたが、これも自分で負担しないといけなくなったりします。ですので、奥様の年収が140万円位ですと、ほぼ確実に年収130万円弱の場合より夫婦の合算の手取りが減ります。10万円分以上のただ働き・・ということになってしまいます。一生懸命仕事したのに、かえって手取りは減り、子どもの保育園の保育料も上がった・・なんてことは絶対に避けたいですよね。
では、どうすればいいのか。方法は2つです。1つ目は、税金の負担と社会保険料の負担の増加を埋めるくらい、奥様が稼ぐことです。目安としては年収160~170万円以上です。ただそうなると、子どもさんが小さくて正社員としては働けない方には厳しい金額です。
となると、第2の方法、奥様の年収を103万円以下に抑える、という方法を取らざるを得なくなります。ひと月の収入を103万円÷12月=85,000円程度に抑える、年末近くなると103万円を超えないように勤務時間を調整する・・・。
この動きこそが、まさに女性の社会進出を阻む大きな壁となっているわけです。
「外れ馬券」をめぐる最高裁判決で税務当局側が敗訴
2015/03/27 16:02:58 税務調査
コメント (0)
昨年話題になったニュースで、「競馬の馬券配当で得た所得を申告していなかった」ため、約6億9,000万円(無申告加算税などを含む)を追徴課税された(!)、というものがあります。競馬の配当は一時所得であり、所得税の課税対象であることは間違いないのですが(一般的に少額のものがどれくらい申告されているかは別として)、納税者と国税局の見解が大きく分かれました。
納税者の主張は、3年間に計約28億7,000万円分の馬券を購入し、計約30億1,000万円の配当を得たので、利益は(差し引きで)約1億4,000万円だ、というものでした。しごくもっともな主張だと思われます。
ところが所得税法の一時所得の規定にはこんな一文があります。「一時所得から差し引ける支出額は、その収入を得るために直接要した金額に限ります」と。
そこで国税局はこう主張しました。「外れ馬券の購入代は、(外れだから、収入を得るための支出ではないので、)その収入を得るために直接要した金額ではない」と。つまり当たり馬券の購入代だけが差し引けるのだから、28億7,000万円のうち当たり馬券の購入代1億1,000万円だけが必要経費で、30億1,000万円-1億1,000万円=29億円(!!)に対して課税する、というものでした。
実は一時所得の規定をあてはめると、国税局の主張は正当なのです。でも、ちょっとまってください。差し引き利益が1億4,000万円の者に6億9,000万円の課税ですと、5億5,000万円も赤字じゃないですか。当然払えるわけありませんよね!?
そこで納税者は弁護士を通してこう主張しました。「この一連の馬券購入は、一時的な収入というよりも、(事業に準ずる規模の)雑所得である。雑所得であれば外れ馬券も、事業全体の必要経費として差し引けるはずである」と。
実はこの納税者は、馬券を自動的に購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいて、インターネットで長期間にわたって多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして、多額の利益を恒常的に上げていました。つまりこれはもう趣味じゃなくて事業でしょう!ということですね。
この度、この税務訴訟に対する最高裁判決が出まして、納税者側の主張が認められました。国が敗訴したわけです。でも、この判例によってすべての馬券収入が雑所得となるわけではなく、「ここまでやってたら」という例外的なものにはなると思います。競馬ファンの方は、お気を付けください。
納税者の主張は、3年間に計約28億7,000万円分の馬券を購入し、計約30億1,000万円の配当を得たので、利益は(差し引きで)約1億4,000万円だ、というものでした。しごくもっともな主張だと思われます。
ところが所得税法の一時所得の規定にはこんな一文があります。「一時所得から差し引ける支出額は、その収入を得るために直接要した金額に限ります」と。
そこで国税局はこう主張しました。「外れ馬券の購入代は、(外れだから、収入を得るための支出ではないので、)その収入を得るために直接要した金額ではない」と。つまり当たり馬券の購入代だけが差し引けるのだから、28億7,000万円のうち当たり馬券の購入代1億1,000万円だけが必要経費で、30億1,000万円-1億1,000万円=29億円(!!)に対して課税する、というものでした。
実は一時所得の規定をあてはめると、国税局の主張は正当なのです。でも、ちょっとまってください。差し引き利益が1億4,000万円の者に6億9,000万円の課税ですと、5億5,000万円も赤字じゃないですか。当然払えるわけありませんよね!?
そこで納税者は弁護士を通してこう主張しました。「この一連の馬券購入は、一時的な収入というよりも、(事業に準ずる規模の)雑所得である。雑所得であれば外れ馬券も、事業全体の必要経費として差し引けるはずである」と。
実はこの納税者は、馬券を自動的に購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいて、インターネットで長期間にわたって多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして、多額の利益を恒常的に上げていました。つまりこれはもう趣味じゃなくて事業でしょう!ということですね。
この度、この税務訴訟に対する最高裁判決が出まして、納税者側の主張が認められました。国が敗訴したわけです。でも、この判例によってすべての馬券収入が雑所得となるわけではなく、「ここまでやってたら」という例外的なものにはなると思います。競馬ファンの方は、お気を付けください。
「投資」と「投機」と「ギャンブル」の違い
2015/03/01 14:36:24 株式投資
コメント (0)
日経平均がとうとう18,000円を突破して参りました。第三の矢はなかなか飛んでこないように思いますが、円安、アメリカ経済の好調、そして日銀金融緩和と年金資金等の買い支えにより株式市場は好況のようです。
NISAなども始まっており、資産運用の一環としての株式投資を始める方も増えてきておりますが、一方で「株は怖い」「株で借金して身を滅ぼす」といったイメージが根強く残っているのも事実だと思います。
私は「ぜひ株を始めて下さい」とお勧めする気はありませんが、「投資」「投機」「ギャンブル」の3つの違いを理解することによって、少なくとも株式投資で借金を抱えるようなことはなくなると思います。
「投資」とは会社の未来の業績UPにより株式価値の上がることを期待して株を買うことで、まっとうな経済活動であると思います。ただし株価というのは業績に連動しているわけでは必ずしもなく、話題性、需要と供給のバランス、特定資金の介入など、複数の要素が絡み合っておるところが悩ましいところです。
「ギャンブル」とは、上がるか下がるか、丁半ばくちのような感覚で株を買うことです。「ここまで下がったら損切りする」というようなリスク管理もなく、することといえば「上がれ」と祈ることだけです。これでは一度二度は利益が出せても、長い目で見れば必ず損をすることでしょう。
「投機」とは、いわば「市場の歪み」を利益に替える行為です。悪い材料が出て市場がパニックになり、あまりにも売られすぎ、というほど株価が下がることがままあります。市場心理が落ち着けば落ち着くべき水準に戻るので、「下がりすぎのところで買い、適正水準に戻ったところで売る」という投資行動により利益が得られます。特に「ギャンブル」と「投機」の違いはよく理解しておく必要があると思います。
「投資」という長期投資と、「投機」という短期投資、そして「ギャンブル」はしない、健全な資産運用ができることを心掛けていきたいですね。
NISAなども始まっており、資産運用の一環としての株式投資を始める方も増えてきておりますが、一方で「株は怖い」「株で借金して身を滅ぼす」といったイメージが根強く残っているのも事実だと思います。
私は「ぜひ株を始めて下さい」とお勧めする気はありませんが、「投資」「投機」「ギャンブル」の3つの違いを理解することによって、少なくとも株式投資で借金を抱えるようなことはなくなると思います。
「投資」とは会社の未来の業績UPにより株式価値の上がることを期待して株を買うことで、まっとうな経済活動であると思います。ただし株価というのは業績に連動しているわけでは必ずしもなく、話題性、需要と供給のバランス、特定資金の介入など、複数の要素が絡み合っておるところが悩ましいところです。
「ギャンブル」とは、上がるか下がるか、丁半ばくちのような感覚で株を買うことです。「ここまで下がったら損切りする」というようなリスク管理もなく、することといえば「上がれ」と祈ることだけです。これでは一度二度は利益が出せても、長い目で見れば必ず損をすることでしょう。
「投機」とは、いわば「市場の歪み」を利益に替える行為です。悪い材料が出て市場がパニックになり、あまりにも売られすぎ、というほど株価が下がることがままあります。市場心理が落ち着けば落ち着くべき水準に戻るので、「下がりすぎのところで買い、適正水準に戻ったところで売る」という投資行動により利益が得られます。特に「ギャンブル」と「投機」の違いはよく理解しておく必要があると思います。
「投資」という長期投資と、「投機」という短期投資、そして「ギャンブル」はしない、健全な資産運用ができることを心掛けていきたいですね。
電子申告の今
2015/03/01 14:32:59 決算書
コメント (0)
確定申告真っ最中の時期ですが、税務署は数年前から電子申告の普及に力を入れており、利便性や安全性も年々向上しているため、今ではずいぶん便利になりました。
自分で確定申告をする場合、今ではすべて手書きで作成する方よりも、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作成したものを印刷し、必要書類をつけて郵送する、という方が増えてきています。返信用封筒を同封すれば、受付印のついた控え書類を返送してくれます。
電子申告はもう少し進んで、源泉徴収票などの書類も添付書類データとして作成すれば提出不要で(保存は必要)、印鑑を押さなくても本人もしくは税理士の電子署名を添付すればペーパーレスで申告が完了してしまいます(一部、原本提出が必須なものもあり)。
ただ税理士に依頼しない場合は、自分で住基カードを取得してバーコードリーダーを買ってくるなど最初に環境を整えるのが手間なため、ややハードルがありました。しかし日経新聞によりますと、2017年からはスマートフォンのSIMカードを利用して、本人認証ができるようになるようです。さらにマイナンバー制度が始まると、医療費情報が共有化されて、医療費の領収書の添付すらなくなるとも言われています。
自分で確定申告をする場合、今ではすべて手書きで作成する方よりも、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作成したものを印刷し、必要書類をつけて郵送する、という方が増えてきています。返信用封筒を同封すれば、受付印のついた控え書類を返送してくれます。
電子申告はもう少し進んで、源泉徴収票などの書類も添付書類データとして作成すれば提出不要で(保存は必要)、印鑑を押さなくても本人もしくは税理士の電子署名を添付すればペーパーレスで申告が完了してしまいます(一部、原本提出が必須なものもあり)。
ただ税理士に依頼しない場合は、自分で住基カードを取得してバーコードリーダーを買ってくるなど最初に環境を整えるのが手間なため、ややハードルがありました。しかし日経新聞によりますと、2017年からはスマートフォンのSIMカードを利用して、本人認証ができるようになるようです。さらにマイナンバー制度が始まると、医療費情報が共有化されて、医療費の領収書の添付すらなくなるとも言われています。
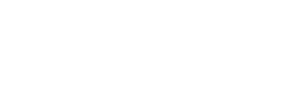

 RSS 2.0
RSS 2.0