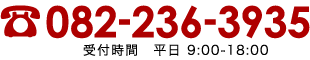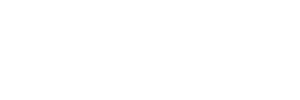ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
広島カープから経営戦略を学ぶ
2017/08/02 18:14:36 経営
コメント (2)
今年もカープは独走態勢に入っております。昨年よりも選手層が厚くなっており、よほどのことがない限り今年もリーグ優勝しそうですよね! ・・そんなカープですが、経営面から見ると40年以上も黒字経営を継続している優良企業です。40年ですから、前回の日本一の時から、そしてその後の低迷期(市民球場がガラガラだった時期(^^;))でも黒字は維持し続けていたわけです。株式会社広島東洋カープは上場企業ではありませんので、あくまでも詳細な決算内容が開示されているわけではありませんが、最近はカープ関連本もたくさん出ていますので、私見を大いに含めて、その秘密を見ていきたいと思います。
株式会社広島東洋カープの株主構成は、マツダ創業者の松田家が40%強、マツダが30%強で、マツダは拒否権を発動できる3分の1以上は所有していないようです。よって、赤字を補填するといった部分までの関与もしていないため、株式会社広島東洋カープは単独で採算を合わせていかないといけない、という大前提があります。そのため黒字継続もそうですが、銀行借入金も比較的少なく、自己資本比率(総資産のうち、借入以外でまかなっている割合)も約60%と財務状況も健全です。
売上面から言いますと、やはり2009年にオープンしたマツダスタジアムの存在が大きく、建設当時はたしか「新球場なんか造って大丈夫?(資金まかなえるの?)」という声も少しあったように記憶していますが、こんな「観客を楽しませる」アイデアが豊富な球場だとは!思いませんでした。収容人員自体は旧広島市民球場より約1,000人増えた33,000人程度なのですが、目先のキャパ(収容力)を広げることよりも、野球観戦をゆったりと楽しめる環境整備を優先し、またマーケティング的には、家族におけるキーパーソンである「女性客」(特にお母さん)をメインターゲットにしたことで、長期的な目線でリピーター顧客(=ファン)を定着させ、高い観客動員数を維持することに成功しています。売上高では2009年に初めて100億円を突破し、2015年には148億円ですから、なかなかの伸びです。広島市の人口が120万人程度で観客動員数が年間200万人以上ですから、広島市に住む全ての人が毎年2回マツダスタジアムに行っている計算(もちろん広島市以外からもたくさんの人が来ていますが)ですから、驚異の「回転率」だと思います。戦後の復興の象徴である地元密着型球団、という個性もかつては「地方の貧乏球団」という位置づけでしたが、今は強烈な個性(=アイデンティティ)としてプラスに働いている感があります。
また、売上増加はグッズ収入の伸びも大きく貢献しており、新球場オープン前である2008年の10億円弱に対して2015年は35億円となっています。これもすごい伸びです。かなり独特で、センスのいいグッズで種類も豊富(三井物産と提携しているそうです)です。個人的には、「野球グッズ」ではなく「カープというコンテンツの関連商品」という目線で作られているところに経営センスを感じます。また、サヨナラ勝ちの数日後には記念Tシャツが販売されるなど、「フットワーク」と「企画力」もすごいです。
※今度気が向けば、売上以外のことも書かせていただきます。
株式会社広島東洋カープの株主構成は、マツダ創業者の松田家が40%強、マツダが30%強で、マツダは拒否権を発動できる3分の1以上は所有していないようです。よって、赤字を補填するといった部分までの関与もしていないため、株式会社広島東洋カープは単独で採算を合わせていかないといけない、という大前提があります。そのため黒字継続もそうですが、銀行借入金も比較的少なく、自己資本比率(総資産のうち、借入以外でまかなっている割合)も約60%と財務状況も健全です。
売上面から言いますと、やはり2009年にオープンしたマツダスタジアムの存在が大きく、建設当時はたしか「新球場なんか造って大丈夫?(資金まかなえるの?)」という声も少しあったように記憶していますが、こんな「観客を楽しませる」アイデアが豊富な球場だとは!思いませんでした。収容人員自体は旧広島市民球場より約1,000人増えた33,000人程度なのですが、目先のキャパ(収容力)を広げることよりも、野球観戦をゆったりと楽しめる環境整備を優先し、またマーケティング的には、家族におけるキーパーソンである「女性客」(特にお母さん)をメインターゲットにしたことで、長期的な目線でリピーター顧客(=ファン)を定着させ、高い観客動員数を維持することに成功しています。売上高では2009年に初めて100億円を突破し、2015年には148億円ですから、なかなかの伸びです。広島市の人口が120万人程度で観客動員数が年間200万人以上ですから、広島市に住む全ての人が毎年2回マツダスタジアムに行っている計算(もちろん広島市以外からもたくさんの人が来ていますが)ですから、驚異の「回転率」だと思います。戦後の復興の象徴である地元密着型球団、という個性もかつては「地方の貧乏球団」という位置づけでしたが、今は強烈な個性(=アイデンティティ)としてプラスに働いている感があります。
また、売上増加はグッズ収入の伸びも大きく貢献しており、新球場オープン前である2008年の10億円弱に対して2015年は35億円となっています。これもすごい伸びです。かなり独特で、センスのいいグッズで種類も豊富(三井物産と提携しているそうです)です。個人的には、「野球グッズ」ではなく「カープというコンテンツの関連商品」という目線で作られているところに経営センスを感じます。また、サヨナラ勝ちの数日後には記念Tシャツが販売されるなど、「フットワーク」と「企画力」もすごいです。
※今度気が向けば、売上以外のことも書かせていただきます。
社内会議のあり方
2017/05/01 15:50:48 経営
コメント (0)
北朝鮮の核問題をめぐり、東アジアでは緊張が高まっています。関係する周辺国では首脳会議が頻繁に行われており、各国の駆け引きが連日新聞やニュースで取り沙汰されています。
・・ところでこの首脳会議、各国の政府最高責任者が一堂に会して行われていますが、実際はこの会議以前に実務者レベルでの話し合い等で、当日話し合う内容はほぼ決まっており、当日は「こういう形で合意したよ」と外部にアピールすることが主目的であると推測できます。何が言いたいかといいますと、首脳会議の当日に「北朝鮮問題、どうします?」という感じになることはありえないということです。
当たり前じゃないかと思われましたか?確かにその通りです。ところで、社内で月例会議等は行われていますか?その冒頭がこんな一言で始まるようでしたら注意が必要です。
「今月の定例会議の議題は何にしますか?議題がある方は挙手してください。」
当日の会議が「どうします?」で始まっています。やはり、会議としては「ありえない」と思います。なぜか。それは、会議の目的は「意思決定」だからです。経営の戦略の決定や、そのための具体的な行動スケジュールの決定、業務の改善のための決め事の決定をして、それを行動に移すことがゴールです。当日の会議で意思決定を行うためには、会議の冒頭が「どうします?」では時間的に間に合いません。
おそらく首脳会費では、その会議が始まる前に物事の99.9%は決定済みだと思います。そこまでいかなくても、社内会議では事前に参加者との個別打ち合わせ、資料作成、スケジュールや大まかな方向性の確認により8割程度は事前に物事が決定しているべきであると私は思います。会議も他の仕事と同様、「段取り八分」です。
また、会議は「会議の終了時間」がゴールではありません。「いやあ、今日も会議、遅くまでご苦労さん」で満足してしまう方は、会議のゴールが「決定事項を行動に移して結果を出す」ところにあると認識していません。だから、会議で決められたことが守られない。行動に移さない。「笛吹けど踊らず」なのは、会議の主催者自体がゴールがどこにあるのかを認識違いしているからかもしれません。
まとめますと、検討→決定→行動の一連の流れがあり、それが「結果」として現れることが会社や事業体がやる会議の「ゴール」です。決して会議をすること自体が会議の目的ではなく、「こんなに頑張って会議しましたよ」と上司や経営者に報告することも会議の目的ではありません。会議は、「参加人数」×「会議時間」という人的資源(コスト)を使って行うものです。決してお金が直接流出していないからといって無駄に使っていいものではありません。
・・ところでこの首脳会議、各国の政府最高責任者が一堂に会して行われていますが、実際はこの会議以前に実務者レベルでの話し合い等で、当日話し合う内容はほぼ決まっており、当日は「こういう形で合意したよ」と外部にアピールすることが主目的であると推測できます。何が言いたいかといいますと、首脳会議の当日に「北朝鮮問題、どうします?」という感じになることはありえないということです。
当たり前じゃないかと思われましたか?確かにその通りです。ところで、社内で月例会議等は行われていますか?その冒頭がこんな一言で始まるようでしたら注意が必要です。
「今月の定例会議の議題は何にしますか?議題がある方は挙手してください。」
当日の会議が「どうします?」で始まっています。やはり、会議としては「ありえない」と思います。なぜか。それは、会議の目的は「意思決定」だからです。経営の戦略の決定や、そのための具体的な行動スケジュールの決定、業務の改善のための決め事の決定をして、それを行動に移すことがゴールです。当日の会議で意思決定を行うためには、会議の冒頭が「どうします?」では時間的に間に合いません。
おそらく首脳会費では、その会議が始まる前に物事の99.9%は決定済みだと思います。そこまでいかなくても、社内会議では事前に参加者との個別打ち合わせ、資料作成、スケジュールや大まかな方向性の確認により8割程度は事前に物事が決定しているべきであると私は思います。会議も他の仕事と同様、「段取り八分」です。
また、会議は「会議の終了時間」がゴールではありません。「いやあ、今日も会議、遅くまでご苦労さん」で満足してしまう方は、会議のゴールが「決定事項を行動に移して結果を出す」ところにあると認識していません。だから、会議で決められたことが守られない。行動に移さない。「笛吹けど踊らず」なのは、会議の主催者自体がゴールがどこにあるのかを認識違いしているからかもしれません。
まとめますと、検討→決定→行動の一連の流れがあり、それが「結果」として現れることが会社や事業体がやる会議の「ゴール」です。決して会議をすること自体が会議の目的ではなく、「こんなに頑張って会議しましたよ」と上司や経営者に報告することも会議の目的ではありません。会議は、「参加人数」×「会議時間」という人的資源(コスト)を使って行うものです。決してお金が直接流出していないからといって無駄に使っていいものではありません。
法人の種類と特徴
2017/03/28 09:52:58 経営
コメント (0)
法人を設立する!と言いましても、今は複数の選択肢があり、以前より設立しやすくなっています。それぞれの特徴やメリット、デメリットを説明させていただきます。
(1)株式会社
最も一般的な法人形態。設立には登録免許税などの諸費用が20万円強かかります。現在では資本金が1円から、役員も1名から設立することができます。
(2)有限会社
平成17年以降は新規設立ができなくなった法人(存続は可)。それまでは法人の設立に、有限会社は300万円、株式会社は1,000万円の資本金が最低でも必要であったため、少ない資本金で法人を設立するためによく選ばれていた形態です。
(3)合同会社
有限会社の設立ができなくなった同時期に新しくできた法人形態。諸費用が10万円程度で設立できる。株式会社と異なるのは出資者と業務執行役員が一体である点で、家族経営なら問題は出にくいですが、多くの出資者から資金を募りたい場合や、資本と経営を分離したい場合は不向きです。
(4)一般社団法人
平成20年以降は諸費用12~18万円程度で誰でも設立できるようになりました。事業内容が特に制限されるわけでもありませんので、法人にパブリックなイメージを与えるために設立するケースのほか、株式が存在しないという法人の特性を生かして相続税対策のために設立する場合もあります。
また、非営利型法人や公益法人として(従来からの社団法人のように)非収益事業について法人税の優遇等を受けることも可能です。
(5)医療法人
現在では医師1人でも設立ができる法人。平成19年以降に設立される医療法人は出資金が「基金拠出型」となっており、基本的には、出資した金額は最終的に国庫に帰属することになっています。そのため、出資金の相続評価が額面金額より上がらないという表裏一体の特徴があります。その名のとおり医療提供行為を目的とした法人で、配当が禁止されている点なども特徴的です。
(6)NPO法人
正式には「特定非営利活動法人」。特定の20種類の分野の活動を行う、一定の要件を満たす法人として認可を受ける必要があります。社会福祉法人ほどの法人税等の優遇はありません。
この他にもたくさんの法人形態がありますが、今回は割愛させていただきます。当事務所では、法人設立のシミュレーションや、提携司法書士と連携して法人設立手続きの代行ができます。お気軽にお問い合わせください。
(1)株式会社
最も一般的な法人形態。設立には登録免許税などの諸費用が20万円強かかります。現在では資本金が1円から、役員も1名から設立することができます。
(2)有限会社
平成17年以降は新規設立ができなくなった法人(存続は可)。それまでは法人の設立に、有限会社は300万円、株式会社は1,000万円の資本金が最低でも必要であったため、少ない資本金で法人を設立するためによく選ばれていた形態です。
(3)合同会社
有限会社の設立ができなくなった同時期に新しくできた法人形態。諸費用が10万円程度で設立できる。株式会社と異なるのは出資者と業務執行役員が一体である点で、家族経営なら問題は出にくいですが、多くの出資者から資金を募りたい場合や、資本と経営を分離したい場合は不向きです。
(4)一般社団法人
平成20年以降は諸費用12~18万円程度で誰でも設立できるようになりました。事業内容が特に制限されるわけでもありませんので、法人にパブリックなイメージを与えるために設立するケースのほか、株式が存在しないという法人の特性を生かして相続税対策のために設立する場合もあります。
また、非営利型法人や公益法人として(従来からの社団法人のように)非収益事業について法人税の優遇等を受けることも可能です。
(5)医療法人
現在では医師1人でも設立ができる法人。平成19年以降に設立される医療法人は出資金が「基金拠出型」となっており、基本的には、出資した金額は最終的に国庫に帰属することになっています。そのため、出資金の相続評価が額面金額より上がらないという表裏一体の特徴があります。その名のとおり医療提供行為を目的とした法人で、配当が禁止されている点なども特徴的です。
(6)NPO法人
正式には「特定非営利活動法人」。特定の20種類の分野の活動を行う、一定の要件を満たす法人として認可を受ける必要があります。社会福祉法人ほどの法人税等の優遇はありません。
この他にもたくさんの法人形態がありますが、今回は割愛させていただきます。当事務所では、法人設立のシミュレーションや、提携司法書士と連携して法人設立手続きの代行ができます。お気軽にお問い合わせください。
東芝の債務超過からみる「選択と集中」の是非
2017/03/04 12:18:52 経営
コメント (0)
東芝といえばサザエさんのスポンサーとしてもおなじみの、100年を優に超える歴史を誇る、日本を代表する大企業のひとつです。その東芝が本年度末決算で債務超過に転落することが決定的で、そして債務超過回避のために稼ぎ頭のフラッシュメモリー事業を分社化して全株式を売却する見込みとか。なぜ巨大企業がここまでの事態になってしまったのでしょうか。
報道によれば、アメリカの原発関連事業で今期7,000億円以上の損失が計上されるそうです。前期も原発関連で2,500億円近く損失を計上していますので、2年間で1兆円にせまるというとてつもない金額の損失額です。原発事業は、東日本大震災以前は花形的な事業で、日本の原発技術を駆使して、世界でたくさんの原子力発電所を建設しようとしていました。とくに日立と東芝が積極的だったと記憶しています。その中で2006年に東芝がアメリカのウェスチングハウスという大手原発メーカーをかなり高い金額で買収しています。そもそもこれが間違いだったのではと今では言われています。
その後、東日本大震災を期に、原発事業は世界的に縮小に入ります。安全性の問題が大きく問われるようになりましたので当然です。それでも東芝は原発事業に強気の姿勢を崩さなかったようです。東芝は家電事業や医療機器事業(これもかなり儲かっていた!)を売却し、原発事業とフラッシュメモリー事業に賭けるという「選択と集中」を行いました。
その結果、アメリカの原発事業は追加建設費用で損失が大きく膨らみ、しかも工事コスト増をこちらで負担するというオプション契約までついていたそうで、撤退するにも多額の違約金が発生し、動きがとれなくなっているようです。そして、とうとう稼ぎ頭のフラッシュメモリー事業を手放すこととなり、これで債務超過を解消できたとしても、もう稼げる事業が東芝には残っていないという事態に陥りそうです。
ここからはえらそうに私見を書かせていただきますが、結果的に東芝は「選択と集中」すべき事業を見誤った、もしくはそもそも「選択と集中」をすべきでなかったのだと思います。原発事業もフラッシュメモリー事業もハイリスクハイリターンの事業だと思うので、一本足打法でこけてしまった液晶事業のシャープと同様、一度こけてしまうと取り返しのつかないようでは企業を永続させるのは難しいと思います。
事業を2本柱にするのであれば、一方が不調の時はもう一方で補える、そんなバランスが求められるのであって、一方がこけたら全て終わりという選択をしてはいけない、というのは私たち中小企業にも当然あてはまることなので、肝に銘じないといけないところです。またいろいろな記事をみていると、そもそも東芝は「選択と集中」をすべきではなかったというものもありました。もともと有望な複数の事業をバランスよく展開する企業だったので、それを続ければよかったのだと。もちろん中小企業が限りある経営資源を特定分野に集中させることはとても有効だと思いますが、その先に事業の水平展開が見えず、いつまでも一本足打法を続けるのは「企業を長く存続させる」ことに必ずしもつながらないのだと思います。
報道によれば、アメリカの原発関連事業で今期7,000億円以上の損失が計上されるそうです。前期も原発関連で2,500億円近く損失を計上していますので、2年間で1兆円にせまるというとてつもない金額の損失額です。原発事業は、東日本大震災以前は花形的な事業で、日本の原発技術を駆使して、世界でたくさんの原子力発電所を建設しようとしていました。とくに日立と東芝が積極的だったと記憶しています。その中で2006年に東芝がアメリカのウェスチングハウスという大手原発メーカーをかなり高い金額で買収しています。そもそもこれが間違いだったのではと今では言われています。
その後、東日本大震災を期に、原発事業は世界的に縮小に入ります。安全性の問題が大きく問われるようになりましたので当然です。それでも東芝は原発事業に強気の姿勢を崩さなかったようです。東芝は家電事業や医療機器事業(これもかなり儲かっていた!)を売却し、原発事業とフラッシュメモリー事業に賭けるという「選択と集中」を行いました。
その結果、アメリカの原発事業は追加建設費用で損失が大きく膨らみ、しかも工事コスト増をこちらで負担するというオプション契約までついていたそうで、撤退するにも多額の違約金が発生し、動きがとれなくなっているようです。そして、とうとう稼ぎ頭のフラッシュメモリー事業を手放すこととなり、これで債務超過を解消できたとしても、もう稼げる事業が東芝には残っていないという事態に陥りそうです。
ここからはえらそうに私見を書かせていただきますが、結果的に東芝は「選択と集中」すべき事業を見誤った、もしくはそもそも「選択と集中」をすべきでなかったのだと思います。原発事業もフラッシュメモリー事業もハイリスクハイリターンの事業だと思うので、一本足打法でこけてしまった液晶事業のシャープと同様、一度こけてしまうと取り返しのつかないようでは企業を永続させるのは難しいと思います。
事業を2本柱にするのであれば、一方が不調の時はもう一方で補える、そんなバランスが求められるのであって、一方がこけたら全て終わりという選択をしてはいけない、というのは私たち中小企業にも当然あてはまることなので、肝に銘じないといけないところです。またいろいろな記事をみていると、そもそも東芝は「選択と集中」をすべきではなかったというものもありました。もともと有望な複数の事業をバランスよく展開する企業だったので、それを続ければよかったのだと。もちろん中小企業が限りある経営資源を特定分野に集中させることはとても有効だと思いますが、その先に事業の水平展開が見えず、いつまでも一本足打法を続けるのは「企業を長く存続させる」ことに必ずしもつながらないのだと思います。
経営のルールの作り方(2)
2016/08/08 15:13:59 経営
コメント (0)
前回、経営のルールの作り方、順番を以下のように定義させていただきました。
(1)経営理念 → (2)経営方針 →(3)戦略 →(4)戦術
(1)の経営理念が、会社の「存在意義」「使命」「旗印」として存在します。今回は、(2)(3)(4)についてご説明させていただきます。
(2)経営方針は、事業の根底となる判断基準です。私は、経営方針とは、市場・経済環境に左右されない、ゆるぎないものでなくてはならいと思います。数値的な方針も、ここでは必要ないと思います。
なぜなら経営方針とは、内部外部の要因により(3)戦略(4)戦術の見直しが必要になった場合に、会社の進むべき方向がぶれないようにするための指針だからです。進むべき方向に迷ったら、経営方針に従う!そのためのものだからです。
日本郵政グループの経営方針の一番目は、「お客様の生活を最優先し、創造性を発揮しお客さまの人生のあらゆるステージで必要とされる商品・サービスを全国ネットワークで提供します。」とあります(同社ホームページより抜粋)。これに従いますと、例えば「採算と合理化のため、○○県から撤退すべきかどうか」の判断に対しては、「NO」という結論が導かれると思います。「全国ネットワークで提供」することが経営方針だからです(あくまで私の解釈です)。では、なぜ「全国で」なのかというと、経営理念たる会社の存在意義が、そうなっているからです。
こう見ますと、では「経営理念」「経営方針」は、意地でも曲げてはいけないものなのか、と聞かれそうですが、私はそれでいいと思います。ここが変わるということは、もうその会社は以前とは別の会社に生まれ変わるということだと思います。それくらい、「経営理念」「経営方針」は絶対的な根っこの部分だと思います。
(3)戦略は、目標達成のための絶対的ルールになります。その戦略に基づいた具体的な行動方針が、(4)戦術になります。「戦術」は、会社ごとに個別に計画していきますが、その基となる戦略は、大きく4つに分類できます。①商品戦略、②マーケティング戦略、③営業戦略、④組織戦略、です。
①商品戦略は、「何を売るか」です。ここで重要なのは、売るものの本質を見誤らないことです。たとえばソフトウェア会社であれば商品は確かに「ソフトウェア」ですが、本当に売るのは「煩雑な業務を効率化するためのソリューション(=解決)」です。保険会社の商品は「保険」ですが本当は「安心感」だったりします。商品を買うお客様の顔が見えているか?に気をつけましょう。
②マーケティング戦略は「どこで売るか」、③営業戦略は「どうやって売るか」、④組織戦略は「その商品を継続的に提供するためのバックボーンたる組織をどのようにするか」、です。この4つは相互に支え合う関係ながらも、全くの別物です。
当事務所では、このような経営のルール作りのお手伝いもさせていただいております。お気軽にお問合せください。
(1)経営理念 → (2)経営方針 →(3)戦略 →(4)戦術
(1)の経営理念が、会社の「存在意義」「使命」「旗印」として存在します。今回は、(2)(3)(4)についてご説明させていただきます。
(2)経営方針は、事業の根底となる判断基準です。私は、経営方針とは、市場・経済環境に左右されない、ゆるぎないものでなくてはならいと思います。数値的な方針も、ここでは必要ないと思います。
なぜなら経営方針とは、内部外部の要因により(3)戦略(4)戦術の見直しが必要になった場合に、会社の進むべき方向がぶれないようにするための指針だからです。進むべき方向に迷ったら、経営方針に従う!そのためのものだからです。
日本郵政グループの経営方針の一番目は、「お客様の生活を最優先し、創造性を発揮しお客さまの人生のあらゆるステージで必要とされる商品・サービスを全国ネットワークで提供します。」とあります(同社ホームページより抜粋)。これに従いますと、例えば「採算と合理化のため、○○県から撤退すべきかどうか」の判断に対しては、「NO」という結論が導かれると思います。「全国ネットワークで提供」することが経営方針だからです(あくまで私の解釈です)。では、なぜ「全国で」なのかというと、経営理念たる会社の存在意義が、そうなっているからです。
こう見ますと、では「経営理念」「経営方針」は、意地でも曲げてはいけないものなのか、と聞かれそうですが、私はそれでいいと思います。ここが変わるということは、もうその会社は以前とは別の会社に生まれ変わるということだと思います。それくらい、「経営理念」「経営方針」は絶対的な根っこの部分だと思います。
(3)戦略は、目標達成のための絶対的ルールになります。その戦略に基づいた具体的な行動方針が、(4)戦術になります。「戦術」は、会社ごとに個別に計画していきますが、その基となる戦略は、大きく4つに分類できます。①商品戦略、②マーケティング戦略、③営業戦略、④組織戦略、です。
①商品戦略は、「何を売るか」です。ここで重要なのは、売るものの本質を見誤らないことです。たとえばソフトウェア会社であれば商品は確かに「ソフトウェア」ですが、本当に売るのは「煩雑な業務を効率化するためのソリューション(=解決)」です。保険会社の商品は「保険」ですが本当は「安心感」だったりします。商品を買うお客様の顔が見えているか?に気をつけましょう。
②マーケティング戦略は「どこで売るか」、③営業戦略は「どうやって売るか」、④組織戦略は「その商品を継続的に提供するためのバックボーンたる組織をどのようにするか」、です。この4つは相互に支え合う関係ながらも、全くの別物です。
当事務所では、このような経営のルール作りのお手伝いもさせていただいております。お気軽にお問合せください。
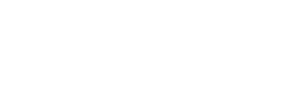

 RSS 2.0
RSS 2.0