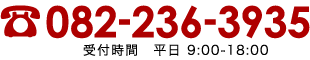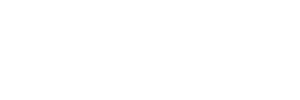ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。
ミニセミナー形式で公開しています。
コロナ関連の経済支援策まとめ(主に持続化給付金)
2020/04/30 17:47:18 経済一般
コメント (0)
コロナウイルスの影響が長期化しております。梅雨ころまでには落ち着けばいいのですが、とにかく今は手持ち資金を厚くしてこの嵐を乗り切ることと、コロナ以後に備えるしかありません。経済産業省から支援策が複数出ており、補正予算も4/30通過しました。まとめます。
(1)持続化給付金 →5/1申請受付開始!(令和3年1/15まで)
今年1~12月のどこかの月で、その月と前年同月とを比較して売上が50%以上下がっていれば法人は200万円、個人は100万円を上限に給付金(返済不要)が1回限り受けられます。業種は問わず、また医療法人やNPO法人も対象になります。
例えば今年3月の売上が120万円、昨年3月の売上が250万円ならば申請可能です。給付額は、3月決算法人ならば前事業年度(H31.3月期)の年間売上高3,000万円とすると、3,000万円-120万円×12=1,560万円が給付算定額で、200万円が上限なので満額200万円が給付されます。給付が受けれそうかわからない場合はまず当事務所の担当者にご相談ください!
申請方法ですが、「持続化給付金」で検索していただき、申請用HPで電子申請してください。基本情報を入力し、法人の場合は必要書類として①別表一(電子申告受付番号の印字のあるもの)と②事業概況説明書(表と裏)、③対象月の売上台帳等、④通帳写し(表面+開いた1・2ページ目)をPDFか、写メなど(JPG)で準備してください。
①②は当事務所からお渡ししている決算申告書一式の中にあります。どれかわからない場合はご連絡ください。③はエクセルで作成した売上集計表などでかまいません(形式は問わない)。また当事務所で会計処理済みの月の場合は売上元帳をPDFでお出しできますのでこれもご連絡ください。
また個人事業者の場合は①は確定申告書第一表、②は青色決算書(白色申告なら不要)と読み替えてください。
(2)コロナ特別融資
直近の月の売上が前年同月比で5%以上減少している場合は日本政策金融公庫で特別融資が受けられます。さらに一定以上の売上減少がある場合は利子補給制度により実質無金利になります(全ての融資が無金利になる、というわけではありません)。また民間金融機関でもセーフティネットによる特別融資があります。
またこの他にも、(3)雇用調整助成金(4)法人税等、社会保険料、固定資産税の納税猶予等、(5)IT導入補助金、さらには一律10万円の給付(あとマスクも)なども控えています。まだ詳細が決まっていないものもありますが、随時情報収集して参ります!
(1)持続化給付金 →5/1申請受付開始!(令和3年1/15まで)
今年1~12月のどこかの月で、その月と前年同月とを比較して売上が50%以上下がっていれば法人は200万円、個人は100万円を上限に給付金(返済不要)が1回限り受けられます。業種は問わず、また医療法人やNPO法人も対象になります。
例えば今年3月の売上が120万円、昨年3月の売上が250万円ならば申請可能です。給付額は、3月決算法人ならば前事業年度(H31.3月期)の年間売上高3,000万円とすると、3,000万円-120万円×12=1,560万円が給付算定額で、200万円が上限なので満額200万円が給付されます。給付が受けれそうかわからない場合はまず当事務所の担当者にご相談ください!
申請方法ですが、「持続化給付金」で検索していただき、申請用HPで電子申請してください。基本情報を入力し、法人の場合は必要書類として①別表一(電子申告受付番号の印字のあるもの)と②事業概況説明書(表と裏)、③対象月の売上台帳等、④通帳写し(表面+開いた1・2ページ目)をPDFか、写メなど(JPG)で準備してください。
①②は当事務所からお渡ししている決算申告書一式の中にあります。どれかわからない場合はご連絡ください。③はエクセルで作成した売上集計表などでかまいません(形式は問わない)。また当事務所で会計処理済みの月の場合は売上元帳をPDFでお出しできますのでこれもご連絡ください。
また個人事業者の場合は①は確定申告書第一表、②は青色決算書(白色申告なら不要)と読み替えてください。
(2)コロナ特別融資
直近の月の売上が前年同月比で5%以上減少している場合は日本政策金融公庫で特別融資が受けられます。さらに一定以上の売上減少がある場合は利子補給制度により実質無金利になります(全ての融資が無金利になる、というわけではありません)。また民間金融機関でもセーフティネットによる特別融資があります。
またこの他にも、(3)雇用調整助成金(4)法人税等、社会保険料、固定資産税の納税猶予等、(5)IT導入補助金、さらには一律10万円の給付(あとマスクも)なども控えています。まだ詳細が決まっていないものもありますが、随時情報収集して参ります!
コロナウイルスの影響で今後の経済はどうなるのか
2020/04/02 10:11:55 経済一般
コメント (0)
最初に、個人の確定申告期限が4/16まで延長されたことに伴い、税金の引落日も、所得税は5/15(金)、消費税は5/19(火)に変更されていますので、お知らせいたします。
さて、コロナウイルスのパンデミックに伴い、特にアメリカに本格的に流行し始めてからは、世界中の株式市場が「リーマンショック超え」と言われるくらい暴落しております。今後経済はどうなってしまうのか・・。考えて行きたいと思います。
まず株価が暴落したのは、コロナウイルスだけが原因ではありません。日本では昨年10月に消費税が10%に増税されており、そのため昨年10-12月の日本のGDPは△7.1%というひどさです。8%に増税した時の反省は全く生かされませんでした。その上に人・物の流れが遮断されるのですから、例えコロナウイルスが今後短期間で落ち着いたとしても、日本経済がすぐに上向きになる材料は少ないです。今後もアメリカと中国に経済を引っ張ってもらう以外にはありません。
またコロナウイルスとは関係ないところで、原油相場が暴落していることはご存じでしょうか?最近ガソリンが安くなっているので、家計には良いのですが、これも世界経済的には深刻な問題で、直接的な理由はサウジアラビアとロシアが原油の減産で話が折り合わず物別れになってしまったからです。
コロナウイルスの影響で経済が停滞し原油の使用量も減少するため、原油を掘る量を減らして価格が下がらないように在庫調整しないといけないのですが、ここ数年で両国が減産している間にアメリカにシェールオイルの増産でシェアを拡大されてしまったという痛い過去があるので、どうせ物別れに終わったならサウジアラビアは「価格が崩れてもいいから増産してアメリカのシェアを取り返してやる」と逆に増産に動きました。このため在庫のだぶつきを懸念した原油相場は過去に例がないほど暴落しました。この暴落によりアメリカのシェールオイル関連企業が窮地に立たされる(原価割れする)ため、関連企業の倒産により経済の低迷に拍車がかかるという話まで出ております。
今回、リーマンショック時との大きな違いがありまして、リーマンショックの時は金融危機がまず起きて、その影響で実態経済が停滞しました。今回はいきなり人・物の動きが止まったため先に実体経済にダメージを受けました。そのため、金融政策(金融緩和や中小企業への無利子貸付など)で時間をかせいでいるうちにコロナウイルスが沈静化すれば、実体経済が持ち直す可能性も高いと思います。その際には、各国が紙幣を大量に刷ってお金がだぶついているでしょうから、さらにインフレになるかもしれません(良いインフレではありませんが)。
しかし停滞が長期化し、金融部分にまで影響が及ぶと、もともと実体経済から先にダメージを受けただけに、もはや金融政策ではどうにもならなくなる可能性もあります。そうならないように祈るばかりです。
さて、コロナウイルスのパンデミックに伴い、特にアメリカに本格的に流行し始めてからは、世界中の株式市場が「リーマンショック超え」と言われるくらい暴落しております。今後経済はどうなってしまうのか・・。考えて行きたいと思います。
まず株価が暴落したのは、コロナウイルスだけが原因ではありません。日本では昨年10月に消費税が10%に増税されており、そのため昨年10-12月の日本のGDPは△7.1%というひどさです。8%に増税した時の反省は全く生かされませんでした。その上に人・物の流れが遮断されるのですから、例えコロナウイルスが今後短期間で落ち着いたとしても、日本経済がすぐに上向きになる材料は少ないです。今後もアメリカと中国に経済を引っ張ってもらう以外にはありません。
またコロナウイルスとは関係ないところで、原油相場が暴落していることはご存じでしょうか?最近ガソリンが安くなっているので、家計には良いのですが、これも世界経済的には深刻な問題で、直接的な理由はサウジアラビアとロシアが原油の減産で話が折り合わず物別れになってしまったからです。
コロナウイルスの影響で経済が停滞し原油の使用量も減少するため、原油を掘る量を減らして価格が下がらないように在庫調整しないといけないのですが、ここ数年で両国が減産している間にアメリカにシェールオイルの増産でシェアを拡大されてしまったという痛い過去があるので、どうせ物別れに終わったならサウジアラビアは「価格が崩れてもいいから増産してアメリカのシェアを取り返してやる」と逆に増産に動きました。このため在庫のだぶつきを懸念した原油相場は過去に例がないほど暴落しました。この暴落によりアメリカのシェールオイル関連企業が窮地に立たされる(原価割れする)ため、関連企業の倒産により経済の低迷に拍車がかかるという話まで出ております。
今回、リーマンショック時との大きな違いがありまして、リーマンショックの時は金融危機がまず起きて、その影響で実態経済が停滞しました。今回はいきなり人・物の動きが止まったため先に実体経済にダメージを受けました。そのため、金融政策(金融緩和や中小企業への無利子貸付など)で時間をかせいでいるうちにコロナウイルスが沈静化すれば、実体経済が持ち直す可能性も高いと思います。その際には、各国が紙幣を大量に刷ってお金がだぶついているでしょうから、さらにインフレになるかもしれません(良いインフレではありませんが)。
しかし停滞が長期化し、金融部分にまで影響が及ぶと、もともと実体経済から先にダメージを受けただけに、もはや金融政策ではどうにもならなくなる可能性もあります。そうならないように祈るばかりです。
10月から消費税は10%!ところでポイント還元ってなあに?
2019/09/30 17:50:32 経済一般
コメント (0)
消費税が10月から10%になりました。5年前に8%になった時、日本の景気は相当落ち込みましたので、今回は「軽減税率」と「ポイント還元」という政策で落ち込みを防ごうとしております。その効果の是非はともかくとして、今回は「ポイント還元」について取り上げてみたいと思います(軽減税率は前月に取り上げました!)。
ポイント還元は、「キャッシュレス決済の普及」とからめての政策で、かつ「中小企業の振興」も含めていますので、詰め込み過ぎて軽減税率以上に訳が分からなくなっています。何度も言いたくないので、先に一度だけ大声で言っておきます。
「そんなに景気が落ち込むのわかってるんなら、消費税上げるなよ!!」・・・
はい、ここからは前向きに行きましょう。令和1年10月~令和2年6月の間に対象店舗でキャッシュレス決済を行うと、購入金額の5%(中小事業者が運営する店舗等)または2%(コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗等)の還元が、値引きやポイント付与という形で受けられるという制度です。対象となる店舗は令和1年9月25日時点で約50万店、また対象となるキャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカード、QRコード決済、電子マネーなどです。対象となる店舗は「キャッシュレスのロゴマーク」が目印になります。
ポイント還元は、「キャッシュレス決済の普及」とからめての政策で、かつ「中小企業の振興」も含めていますので、詰め込み過ぎて軽減税率以上に訳が分からなくなっています。何度も言いたくないので、先に一度だけ大声で言っておきます。
「そんなに景気が落ち込むのわかってるんなら、消費税上げるなよ!!」・・・
はい、ここからは前向きに行きましょう。令和1年10月~令和2年6月の間に対象店舗でキャッシュレス決済を行うと、購入金額の5%(中小事業者が運営する店舗等)または2%(コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗等)の還元が、値引きやポイント付与という形で受けられるという制度です。対象となる店舗は令和1年9月25日時点で約50万店、また対象となるキャッシュレス決済とは、クレジットカード、デビットカード、QRコード決済、電子マネーなどです。対象となる店舗は「キャッシュレスのロゴマーク」が目印になります。
10月から消費税は10%!ところで軽減税率ってなあに?
2019/09/02 18:40:00 経済一般
コメント (0)
どうやら、消費税は予定通り10月から10%に上がりそうです。それに伴って軽減税率制度も始まります。食料品(酒類を除く)の購入、食品の持ち帰り(テイクアウト含む)、新聞の定期購読に限り、引き続き消費税は8%です。新聞だけが8%維持されるのは、政治的な臭いがプンプンしますが、それは置いといて、「じゃあこの時はどうなるの?」というのをピックアップしてご紹介します。しかし「労多く益少なし」とはこの軽減税率制度のようなことを言うのですね・・
①外食は?→対象外の10%
②出前・宅配は?→8%(食品の持ち帰りに該当)
③ウォーターサーバーのレンタル料は?→「水」自体は食品に含むが、レンタル料は役務の提供に該当するため10%
④みりんは?→酒に該当で10%、ただし「みりん風調味料」は8%
⑤ノンアルコール飲料は?→酒に該当しないので8%
⑥栄養ドリンク(医薬部外品)は?→医薬部外品は食品に該当しないので10%
⑦ケーキ屋さんでついてくる保冷剤は?→別途料金を取っていなければケーキと一体で8%(逆に言うと別途料金をとる場合は10%)。持ち帰り用の容器なども同様
⑧食品卸業者がレストランに卸す食品は?→食品には変わりないので8%
⑨セルフサービス店での飲食の提供は?→机、いす等の飲食設備を利用させるので10%
⑩屋台での飲食の提供は?→机、いす等を準備していなければ8%
⑪コンビニのイートインコーナーでの飲食は? →原則は、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%。判定は、販売時に顧客に意思確認すること。ただし持ち帰りが大多数の場合は、「イートインコーナーを利用する場合は申し出てください」等の掲示をしておき、顧客からの意思表示があった場合のみ10%とすることも可。(さて、「持ち帰ります」といった顧客が店内で食べ始めたらどうしますかね(^^;) )
⑫某ハンバーガー店でセットでついてくる「おもちゃ」 →おもちゃを非売品として別途料金を取っていないなら食品と一体で8%
上記は全て国税庁Q&Aに出ています。細かく見れば見るほど不思議な制度ですねーー(^^;)
①外食は?→対象外の10%
②出前・宅配は?→8%(食品の持ち帰りに該当)
③ウォーターサーバーのレンタル料は?→「水」自体は食品に含むが、レンタル料は役務の提供に該当するため10%
④みりんは?→酒に該当で10%、ただし「みりん風調味料」は8%
⑤ノンアルコール飲料は?→酒に該当しないので8%
⑥栄養ドリンク(医薬部外品)は?→医薬部外品は食品に該当しないので10%
⑦ケーキ屋さんでついてくる保冷剤は?→別途料金を取っていなければケーキと一体で8%(逆に言うと別途料金をとる場合は10%)。持ち帰り用の容器なども同様
⑧食品卸業者がレストランに卸す食品は?→食品には変わりないので8%
⑨セルフサービス店での飲食の提供は?→机、いす等の飲食設備を利用させるので10%
⑩屋台での飲食の提供は?→机、いす等を準備していなければ8%
⑪コンビニのイートインコーナーでの飲食は? →原則は、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%。判定は、販売時に顧客に意思確認すること。ただし持ち帰りが大多数の場合は、「イートインコーナーを利用する場合は申し出てください」等の掲示をしておき、顧客からの意思表示があった場合のみ10%とすることも可。(さて、「持ち帰ります」といった顧客が店内で食べ始めたらどうしますかね(^^;) )
⑫某ハンバーガー店でセットでついてくる「おもちゃ」 →おもちゃを非売品として別途料金を取っていないなら食品と一体で8%
上記は全て国税庁Q&Aに出ています。細かく見れば見るほど不思議な制度ですねーー(^^;)
消費税増税で令和は暗雲スタート(>_<)
2019/04/30 17:06:20 経済一般
コメント (0)
新年号「令和」、最近ようやくWordやスマホがダイレクトに変換してくれるようになってきました。めでたいことだとは思いますが、私的にはそれよりも10月の消費税10%が今年の最大のイベントです。今だに「増税再々々先送り論」がくすぶってますが、なぜでしょうか?それは、間違いなく景気に水を差すからです。
消費税が8%に増税されたのは平成26年4月ですが、その年の4-6月の日本の実質GDPは年率-6.8%です。歴史に学ぶ、という言葉を出すまでもなく、消費税の税収増など軽く吹っ飛ばす数値ですよね。10%にしたら財政が再建できるとでも本気で考えているのでしょうか?来年の東京オリンピックまで景気はもつと信じて、(その先のことはとりあえず考えずに)日本経済は走っているわけですが、中国の経済も持ち直しの兆しがでてきたので何とかなるかな、というところに消費税増税という時限爆弾が爆発したらどうなるか・・。地方選に敗れた自民党が「増税先送り+衆参ダブル選挙」と言うのもあながち暴論ではないと私は思います。
特に事業者目線からしますと、消費税の8%→10%は2%の増税ではなく、8%×1.25=10%と
25%の増税なわけですから、「消費税は預り金です」と正論を言われても肌感覚的にそれで納得するはずもないことはこの30年間で証明済みで、「景気の先行き不透明感+実質大増税」でまたも景気は低迷・・令和に替わってもそんなことを繰り返すわけです。
さらに軽減税率制度というのも10月から実施予定ですが、これがまた○○もいいところ・・(>_<)こんなものを導入しないと上げれない消費税なら最初から上げるな!と共産党支持者でなくとも言いたくなります。いったい消費税制度を無意味に複雑にして何がしたいんでしょうか。税理士の仕事を増やして税理士の既得権を国を挙げて守ってくれているのでしょうね。ホンマ、ありがたいことですわ。
一応軽減税率制度の説明をさせていただきますと、増税後も飲食料品と(なぜか)新聞の定期購読は引き続き8%です。軽減される飲食料品には、テイクアウト・宅配等は含まれ、酒類・外食等は含まれません。新聞等でよく議題に上がっていたのが、「コンビニで飲食料品を購入して、持ち帰れば8%だが、そのままイートインコーナーで食べると外食に該当するので10%。これをレジでの支払段階でどちらと判断するの?」という話でした。
結論は、コンビニは「イートインを利用される方は申し出てください」と張り紙しておき、レジで購入者に意思確認して判断。たとえ「持ち帰る」と答えて8%払った後イートインで食べても法律上咎めることはできないようで、法理論が破たんしているような・・。
消費税が8%に増税されたのは平成26年4月ですが、その年の4-6月の日本の実質GDPは年率-6.8%です。歴史に学ぶ、という言葉を出すまでもなく、消費税の税収増など軽く吹っ飛ばす数値ですよね。10%にしたら財政が再建できるとでも本気で考えているのでしょうか?来年の東京オリンピックまで景気はもつと信じて、(その先のことはとりあえず考えずに)日本経済は走っているわけですが、中国の経済も持ち直しの兆しがでてきたので何とかなるかな、というところに消費税増税という時限爆弾が爆発したらどうなるか・・。地方選に敗れた自民党が「増税先送り+衆参ダブル選挙」と言うのもあながち暴論ではないと私は思います。
特に事業者目線からしますと、消費税の8%→10%は2%の増税ではなく、8%×1.25=10%と
25%の増税なわけですから、「消費税は預り金です」と正論を言われても肌感覚的にそれで納得するはずもないことはこの30年間で証明済みで、「景気の先行き不透明感+実質大増税」でまたも景気は低迷・・令和に替わってもそんなことを繰り返すわけです。
さらに軽減税率制度というのも10月から実施予定ですが、これがまた○○もいいところ・・(>_<)こんなものを導入しないと上げれない消費税なら最初から上げるな!と共産党支持者でなくとも言いたくなります。いったい消費税制度を無意味に複雑にして何がしたいんでしょうか。税理士の仕事を増やして税理士の既得権を国を挙げて守ってくれているのでしょうね。ホンマ、ありがたいことですわ。
一応軽減税率制度の説明をさせていただきますと、増税後も飲食料品と(なぜか)新聞の定期購読は引き続き8%です。軽減される飲食料品には、テイクアウト・宅配等は含まれ、酒類・外食等は含まれません。新聞等でよく議題に上がっていたのが、「コンビニで飲食料品を購入して、持ち帰れば8%だが、そのままイートインコーナーで食べると外食に該当するので10%。これをレジでの支払段階でどちらと判断するの?」という話でした。
結論は、コンビニは「イートインを利用される方は申し出てください」と張り紙しておき、レジで購入者に意思確認して判断。たとえ「持ち帰る」と答えて8%払った後イートインで食べても法律上咎めることはできないようで、法理論が破たんしているような・・。
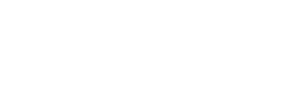

 RSS 2.0
RSS 2.0